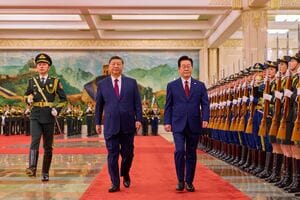「これ以上は危険、でもギリギリまで前進したい」のせめぎ合い
火砕流が発生する前のことだ。取材地点を決める市の対策本部とプレス側の調整は難航したという。プレス側は少しでも現場に近づきたい、市は当然の事として安全確保を主張する。結局、プレス側の多くは「避難勧告」に従わず、「定点」でカメラを構えた。ギリギリまで近づきたい、少しでも絵になる取材をしたい、という剥き出しの好奇心、取材競争は報道カメラマンの性(さが)だが、その性があの大惨劇を生むことになった。
巻き添えになった人達がいることで、報道のあり方に強い非難が集まった。これを契機に、報道機関の側も取材のあり方を考え直しはじめた。
しかし、取材現場での実際の判断は難しい。「危険だ」と言われてもついつい「もう少しだけ先に」と考えるものなのだ。取材の最前線にいる瞬間は、周りの誰よりも早く、そして迫力あるシーンを撮りたいと思う。これはカメラマンの本能だ。性と言ってもいい。
その性と、法律や社会規範、報道各社が定めたルールなどとが心の中でせめぎ合う。あの火砕流以降、その規範やルールは確実に厳格になった。
ただ雲仙普賢岳のときには、おそらく誰も火砕流の恐ろしさを理解していなかったと思う。高名な火山学者も一緒にいることで安心した面もあるのかもしれない。
時代は変わり、報道のあり方も変わってきたが、あの頃はどこの現場でも、さほど厳しい規範やルールはなく、混沌としていた。逆に言えば、それだけ活気が溢れていた、ように思う。