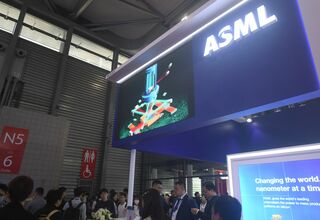溥儀擁立で「正当な政権」をアピール
満洲国建国の最大のハイライトは、清朝の廃帝である愛新覚羅溥儀(あいしんかくら ふぎ)の擁立だろう。1906年(明治39年)生まれの溥儀は3歳のときに清朝第12
残り6255文字
満洲国建国の最大のハイライトは、清朝の廃帝である愛新覚羅溥儀(あいしんかくら ふぎ)の擁立だろう。1906年(明治39年)生まれの溥儀は3歳のときに清朝第12
残り6255文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら