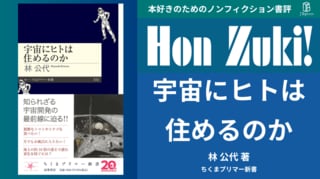これは地方の小さな「弁当屋」を大手コンビニチェーンに弁当を供給する一大産業に育てた男の物語である。登場人物は仮名だが、ストーリーは事実に基づいている(毎週月曜日連載中)。
前回の記事はこちら(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/60846)
昭和53年~54年:31歳~32歳
澤井社長は北原屋の社長を務める傍ら、業界団体の役職などを幾つも兼務し、忙しく動き回っていた。都内に点在する現場は、それぞれの責任者に大幅な権限を与え時折顔を出すだけだったが、その演出が実に見事だった。
繁忙期あるいは閑散期を捉えて、絶妙のタイミングで澤井社長はふらりと現れる。訪れる際はいつも手ぶらではなく、ドリンク剤であったり果物やケーキであったり、心憎い手土産を持参する。
そのタイムリーさに感嘆した旨を村野常務に伝えると、
「本川さんだから、教えるけれど…」そう断ったうえで、耳打ちされた。
「社長訪問のタイミングやお土産の品は、全て現場責任者からの要請なんだよ」
(成程!そうだったのか…)とは言え、そう仕向けたのは社長だろうから、やはり卓越した人心掌握である。
ある時、澤井社長に北原屋の年商を訊ねたことがある。
「昨年の売上は、55億円ほどだ」
即座に答えられたが、同席していた村野常務が後からこっそり教えてくれた。
「当社の年商は、正確には49億3千万円ですよ。うちの社長には妙な見栄が在って、何でも少しずつ大袈裟に話すんだよね」
その口ぶりには社長を非難する気配は微塵も無く、むしろ見栄を張る社長を慈しむようにすら感じられ、恭平は二人の人柄と二人の関係を羨んだ。
北原屋での研修も3カ月を過ぎた頃、恭平は何か恩返しをしたくて、「昔取った杵柄」ならぬ、「直前までのコピーライター経験」を活かして、製造マニュアルや営業ツールの作成を思い立ち、村野常務に提案した。
製造の現場で痛感したことは、とにかく自分の次に作業する人の立場に立って考え行動することの大切さだった。そうすることで結果として自分もラクができ、組織全体の成果にも繋がる。
例えて言えば、調理の担当者は盛付けの担当者が盛付けし易いように気を配り、盛付の担当者は配送者が配り易いように気を配る。さらに俯瞰して言えば、製造者は常にお客様の立場に立って、お客様が喜んでいただけるよう工夫を凝らす。
そうすることで全体の流れがスムーズになり、結果として全員がハッピーになるという図式だ。
恭平が、「次工程はお客様」などと言う生産現場の慣用句を耳にするのは、この研修から数年も後だった。
でも、言葉から入って理解する知識と、実体験で失敗を重ねて習得した知恵は、同じ言葉の重さにも雲泥の差があると思い知らされ、何事も現場が一番で、現場を大切にしない経営はリスクを招きかねないとも実感させられた。
相変わらず不勉強な恭平は、「三現主義」と言う言葉の存在すら未だ知らなかった。