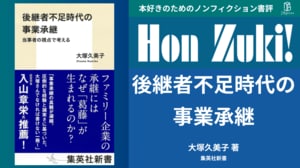砥上裕將 『線は、僕を描く』
描こうとすれば、遠ざかる。
残り1616文字
主人公は、大学生の青山霜介。高校時代に両親を亡くし、生きる気力を失った彼は、未来への意思を持てないまま、周囲に流されるようにしてただ大学に足を運んでいるだけの状態だ。
そんなある日、ひょんなことから彼は、水墨画と出会う。もちろん、今まで見たことも描いてみたこともない。しかしなぜか、水墨画の巨匠と呼ばれ、美術の教科書にも載っている篠田湖山に気に入られ、内弟子にさせられてしまった。
その場で、湖山の孫娘であり、自身も水墨画家である篠田千瑛とも挨拶を交わす。が、彼女から、祖父は内弟子などほとんどとったことがない、なぜあなたが?と怪訝な視線を向けられることになる。まあそうだろう。青山自身が、なぜ湖山に声を掛けてもらえたのか、まったく理解できないのだから。
その場の成り行き上、来年の湖山賞で、青山と千瑛は勝負する、という話になってしまった。水墨画の経験など一切ない青山に勝てるはずもないが、湖山は面白がってその勝負を受けてしまう。
そこから湖山の元へと通い、水墨画の何たるかも分からないまま筆を持ち、手を動かしていく青山だが、その経験が彼の人生観を大きく変えていくことになる・・・。
「絵を描くには技術がいる」
水墨画をテーマにしているという点が非常に目新しいが、基本的には青春小説と捉えていいだろう。しかし、青山が飛び込むことになる水墨画の世界は奥深く、読み進めていくほど、青春小説としての趣から遠ざかっていく。そして、水墨画の世界観に入り込んでいくことで、「捉える(理解する)」ということの認識を深めていくことができるのだ。
青山は、最初は水墨画を「技術」であると捉えていた。冒頭の話に寄せれば、アウトプットの能力、ということだ。当然だろう。絵を描くためには技術がなければ不可能だろうし、技術を高めれば高めるほどより明確に対象を描くことができる、と考えることは自然だと思う。