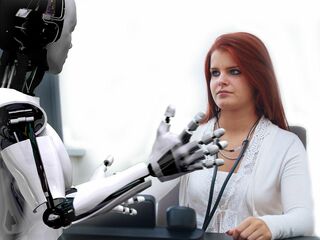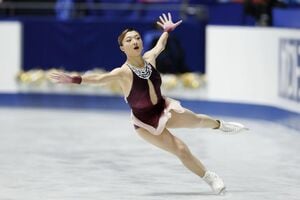米メジャー・リーグでは体の出来上がった大人の投手が100球目処で降板する。次にマウンドに上がるのは5日後だ。登板日から4日置くので「中4日」と呼ばれる。先発ピッチャーが140球近く投げることが多い日本のプロ野球は「中5日」ないし「中6日」が主流である。
スポーツ医学の常識が通じない高校野球の世界
登板間隔を開けるのは、医学的な理由がある。100球以上投げる先発投手の肘や肩周辺の筋肉は毛細血管が切れ、元の状態に戻るのに4日以上かかる。元に戻る前に投げると、故障の原因になるのだ。先発して9回を投げ切った投手が翌日も投げる、というのはプロの世界ではあり得ない。
だから筒香は「子どもたちが無理をしすぎて手術をしたり、けがをして野球を断念したりしたケースを何度も見てきた」と警鐘を鳴らしたのだ。
 日本外国特派員協会で会見し、高校野球のあり方に疑問を呈した横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智選手(写真:Natsuki Sakai/アフロ)
日本外国特派員協会で会見し、高校野球のあり方に疑問を呈した横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智選手(写真:Natsuki Sakai/アフロ)
「連投などもってのほか」。スポーツ医学ではそれが常識だが、日本の少年野球や高校野球では、指導者がエースを平気で連投させる。2週間に7試合というハイペースで投げ続けた吉田は、大阪桐蔭との決勝戦、序盤から足が上がっていなかった。気力を振り絞って投げる球には威力がなく、桐蔭打線に滅多打ちにされる。そして6回、控え投手にマウンドを譲った。
信じられないことに、満身創痍の吉田はベンチに戻らず、外野の守備についた。酷使した肘や肩の炎症を抑えるため、投げ終わった投手はすぐ「アイシング」で肩を冷やすのが常識だが、それもさせず野手としてグランドに残したのだ。控え投手が打たれたら、吉田を灼熱のマウンドに戻すつもりだったのだろうか。
「狂気の連投」を許した金足農業の中泉一豊監督は、試合後のインタビューでこう語っている。
「ずっと吉田でやってきて信じていたが、できれば最後まで投げさせてやりたかった」
この人は、スポーツ医学を全く学んでいないのかもしれない。エースを信頼するとかしないとか、そういう次元の話ではない。記録的な暑さの中での連投は、吉田の投手生命を危うくするばかりでなく、熱中症で命を落とす危険すらある。吉田を見殺しにしたのは中泉だけではない。普段、学校の運動会で熱中症の子どもが出れば、鬼の首を取ったように「監督責任」を問う新聞が、甲子園に限っては「猛暑」も「連投」もスルーなのだ。