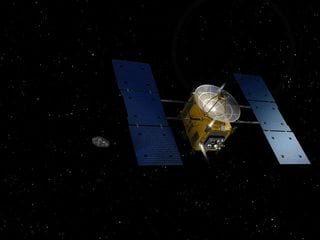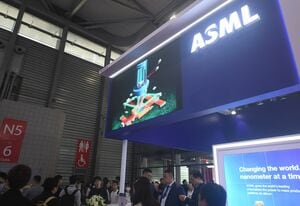例えば、2012年にiPS細胞の研究でノーベル医学・生理学賞を受賞した山中伸弥氏は、ノーベル賞受賞時は京大に在籍していたが、学歴としては神戸大学の医学部を卒業し、大阪市立大学大学院で修士および博士号を取得したため、上記分類では「神戸大学」ということになる。
さて、図1からは、以下の傾向を読み取ることができる。
(1)2000年を過ぎてから受賞者が増大している。2000年以前は、1949年の湯川秀樹氏から1994年の大江健三郎氏まで8人、つまり、45年間で8人(5.6年に1人)しかいないが、2000年以降は、18年間で19人(ほぼ毎年1人)が受賞している。
(2)出身大学別では、東大8人、京大7人、名古屋大3人の順となっている。自然科学3分野に限れば、京大7人、東大6人、名古屋大3人の順となる。
(3)自然科学3分野に限ると、東大、名古屋大などが2000年以降に集中しているのに対して、京大だけが1949年の湯川氏以降、散発的に受賞している。湯川氏以降、69年間で7人の受賞者であるから、ほぼ10年で1人のペースとなっている。
以上から、京大は、「自然科学分野のノーベル賞受賞者が最も多く、ほぼ10年に1人の割合で受賞者が出現する」というユニークな特徴を持つことが分かる。
では、なぜ、京大がこのような特徴を持つのだろうか?
筆者の体験談による私見
筆者は、1981~1987年までの6年間、京大に在籍した。その皮膚感覚からすれば、この特徴が腑に落ちるのである。その根拠は以下の通りである。
京大に入学してまず感じたことは、「こんなに自由でいいのか?」ということだった。何の拘束もないことに眩暈すら覚えた。教養の2年間は外国語と体育さえサボらなければ、後は何をしていても良かった。名物数学教授だった故・森毅氏などは、「大学生のくせに講義なんか出るな」とまで言っていた。だから、ほとんどの学生がバイトやサークルや遊びにうつつを抜かしていた。
ところが、あまりにも自由だからこそ、それを利して徹底的に勉学に励む学生もわずかながらいた。典型例として、湯川秀樹に心酔して理学部に入学し、1回生からランダウ・リフシッツの『量子力学』などを読みこなし、4回生や大学院のゼミにまで顔を出すような猛者が存在した(なぜか関西系の大学では、“○年生”のことを“○回生”と呼ぶ)。このようなスーパー勉学者がノーベル賞級の学者になるのかもしれないと思うのだ。