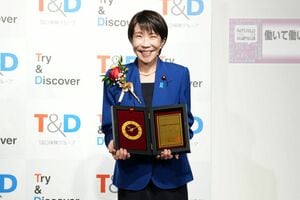大学の教職課程が突きつけられている「変化」とは。
大学の教職課程が突きつけられている「変化」とは。
この2年あまり、全国の大学で教員養成にかかわる教職員の頭を悩ませ、時には憤りを感じさせてきた文部科学省の政策がある。教職課程の再課程認定が、それである。簡単に言ってしまうと、文科省によって、教職課程の運営に関する大学の自主性・自律性を損なうような統制が加えられようとしているのである。
再課程認定の申請は、今(2018年3月時点)始まったばかりなので、今後、審査が進むにつれて、新たな問題が浮上してくる可能性も否定はできない。しかし、ひとまず現段階までのところで、今回の再課程認定をめぐる問題をまとめておきたい。
教員養成制度の「開放制」の原則
やや遠回りにはなるのだが、今起きている事態の性格を的確にご理解いただくために、大学における教育養成の仕組みについて説明しておく。
戦後の大学による教員養成制度は、「開放制」と呼ばれる原則によって運営されている。戦前の教育においては、教員養成の機能は、師範学校および高等師範学校(厳密に言えば、さらに、帝国大学のもとに置かれた臨時教員養成所)によって独占されていた。
ごく一部では、私立大学の専門部に師範科や高等師範科を置くことが認められた時期もあったが、師範学校および高等師範学校は、すべて官立の学校であり、初等・中等教育の学校の教員の圧倒的な大多数は、官立の師範学校および高等師範学校の出身者で占められていたと言ってよい。
戦後は、こうした「閉鎖的」な教育養成制度を解体し、教育系の大学や教育学部でなくても、すべての国・公・私立大学の学部で教員養成が行えるようになった。これが、「開放制」の原則である。
教員養成の方針における180度の大転換であるが、なぜそのような転換が図られたのか。それは、戦前の教育とそれを担った教員の養成についての痛切な反省に端を発している。