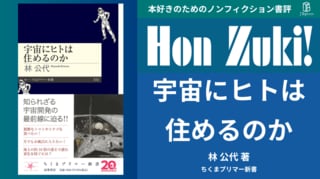和食が、ユネスコの無形文化遺産に登録される見通しだ。来月12月初旬、アゼルバイジャンで開かれる政府間委員会で最終決定となる。
和食を和食たらしめている要素は様々ある。盛りつけの美しさ、健康にもつながる質素さなどだ。そうした中で、和食の味を特徴づけるものとして欠かせないのが、“だし”だろう。日本の周囲で取れる食材を煮出してうまみのある汁にし、これを煮物、汁物、炊き物と様々な料理に使う。まさに和食の基本だ。
世界にも、だしに相当する汁はある。フランスのフォン・ド・ボーや、中国の鶏がらスープなど。ただしこれらには動物由来の食材も使われている。一方、植物のみからだしをとる食文化が日本にはある。
今回は、だしの素材の中でも植物由来の「昆布」に焦点を当てて、その歩みを過去から現代にかけて追っていくことにしたい。福井県の敦賀で1871(明治4)年に創業した老舗昆布問屋「奥井海生堂」の社長、奥井隆氏に話を聞いた。
前篇では、日本で昆布がどのように取り入れられ、そして和食の基本的要素となっていったか、その移り変わりを追っていく。後篇では、この老舗昆布問屋が守り続けている伝統的な昆布加工法に目を向けてみたい。現代の科学的観点からもその加工の効果の裏付けが進んでいるという。
 乾燥させた昆布。食材のスピーディな輸送技術がなかった時代、昆布をはじめとする乾物が産地から消費地へ流通した。 (画像提供:奥井海生堂)
乾燥させた昆布。食材のスピーディな輸送技術がなかった時代、昆布をはじめとする乾物が産地から消費地へ流通した。 (画像提供:奥井海生堂)