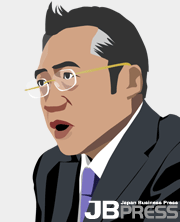世界の株式市場は、2007年から2009年まで3年連続で「3月の波乱症状」に見舞われた。
2007年は2月27日に上海株式市場が8%以上の暴落を演じた「上海ショック」、2008年は米証券大手ベアー・スターンズの経営危機、2009年はリーマン・ショックの余波──。
それぞれに「引き金」となった出来事は異なるものの、信用不安は年を追うごとに膨張し、日経平均株価は2007年3月5日、2008年3月17日、2009年3月10日と相場史に残る安値を付けた。
「上海ショック」からバブル崩壊は始まった
バブルの崩壊は上海市場から始まった〔AFPBB News〕
「上海ショック」が発生した2007年春、日経平均株価は1万8000円台の高値圏にあった。そのためか、5営業日で計9%も急落しても、市場の危機意識は乏しかった。
「あれが過剰流動性が築き上げたバブルの崩壊の始まりだった!」と多くの人が気付くのは、だいぶ時間が経ってからのことだった。それから1年以上が経って世界経済は「100年に1度」の津波に襲われたが、その震源は間違いなく「上海」だった。
米国では「Massacre of October=10月の虐殺」という相場格言があるほど、過去の歴史的暴落は10月に起こることが多かった。しかし、このところは、市場にとって3月も縁起の悪い月となっている。
今年の3月も、「波乱」は繰り返されるのだろうか。
破綻したリーマン・ブラザーズ。AIGと明暗を分けた〔AFPBB News〕
バブルが弾けた時、バブルに踊った民間金融機関が損失を負うのは当然のことだ。しかし、資本主義経済における金融システムの担い手は彼らであり、それがまたボーダーレスかつ複雑に連携しているのが、現代という時代である。
自己責任原則を墨守して自然淘汰に任せていては、金融機関のみならず金融システムまでをも破綻に追い込んでしまうことになる。債務超過を埋め合わせるために公的な支援を行うのは、緊急措置としてやむを得ないと言えるだろう。
納税者の厳しい視線を浴びながらも、金融機関は膨大な損失を国家財政によって肩代わりしてもらうことで生き延びた。一方、各国政府は、実体経済の急減速に対応するための財政出動も強いられてきた。