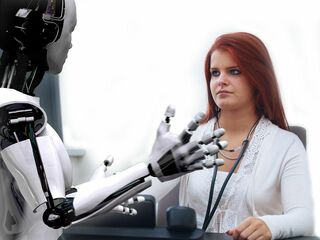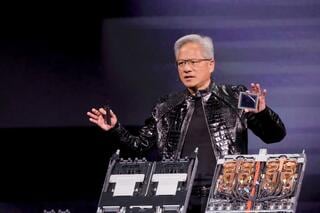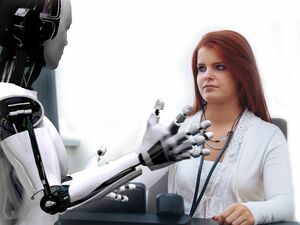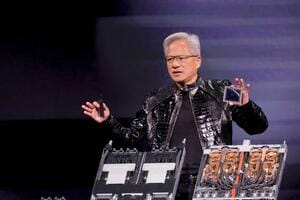「口実」か「構造変化」か――氷山の下に隠れた圧力
しかし、この「AIリストラ」の真実味については、専門家の間で見解が分かれていた。
英オックスフォード・インターネット研究所のファビアン・ステファニー助教は、パンデミック下の過剰採用を調整するために、AIが「格好の口実」として引き合いに出されていると指摘した。
企業にとって「数年前に施策を誤った」と認めるよりも、「AIという革新的な技術のせいで人員が不要になった」とするほうが、投資家への体裁が良いという側面は否定できない。
だが、その「言い逃れ」の裏には、より深刻な構造変化が潜んでいる。
米マサチューセッツ工科大学(MIT)が発表した「アイスバーグ・インデックス(氷山指数)」によれば、ニュースで取り上げられるテック企業の人員削減は氷山の一角(約2%)に過ぎない。
水面下では、人事、経理、物流、業務管理といった「定型的な事務機能」が、米労働市場の11.7%(賃金換算で1兆2000億ドル=約188兆円相当)にわたってAIによる代替圧力を受け続けている。
2025年の数字は、水面下にあったその巨大な塊が、ついに海面上へと姿を現し始めた結果といえる。
突きつけられた「経験格差」と「OJTの崩壊」
2026年を迎えた今、私たちが直面している最大の課題は、人員削減そのものではなく、その「質的変化」だ。
米スタンフォード大学の研究が「炭鉱のカナリア」として警告したように、AIの影響は22〜25歳の若年層に不均衡に重くのしかかる。
AIが得意とするのは「形式知」の処理であり、これは本来、若手社員が実務経験を通じてスキルを習得する「入り口(エントリーレベル)」の業務と重なる。
効率化の名の下にこれら業務をAIに委譲した結果、若者が「暗黙知(経験に基づく知識)」を学ぶための現場が消失しつつある。
米ハーバード大学の研究が示す「サイバネティック・チームメイト」の調査結果も、このジレンマを裏付けている。
AIはチームの生産性を向上させ、専門性の壁を取り払う触媒となる一方で、成果物の「同質化」を招き、ベテランによる若手への「指導の放棄」を誘発する恐れがある。
AIを使えば若手でも「平均点以上」の成果を出せるため、企業がコストをかけて若手を育成するインセンティブが低下しているとの指摘がある。