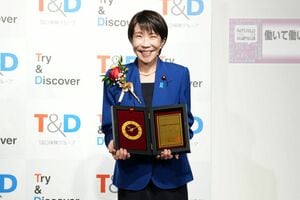私立大入学者の6割近くが学校推薦型・総合型選抜(旧AO入試)で大学合格を決めている(写真はイメージ、mapo_japan/Shutterstock.com)
私立大入学者の6割近くが学校推薦型・総合型選抜(旧AO入試)で大学合格を決めている(写真はイメージ、mapo_japan/Shutterstock.com)
(千田 有紀:武蔵大学社会学部教授)
一般入試に臨む受験生がマイノリティになっていく
文部科学省は大学入試において、大学が求める学生を学力以外の要素で多角的に評価して判断する総合型選抜(旧AO入試)や推薦入試といった年内入試を増やすことが望ましいと考えているらしい。
大学の経営という視点から見れば、これは望ましい形態だ。一般入試の「歩留まり」を読むのは非常に難しい作業であるし、早期に入学者を確保できるのであれば、非常にありがたい。こうした文科省と大学との双方の思惑が交差したところで、これから年内入試はどんどん増加していくだろう。
早稲田大学は2026年、年内入試の割合を6割にするという。いわゆるペーパーテストの入学試験を受けて入る受験生は、マイノリティになっていくかもしれない。となれば大学側は、この少子化の時代に「よりよい学生」をいち早く確保したいとますます考えるようになり、さらにこの風潮は加速していくだろう。
日本の教育などでの選抜システムを、「ご破算型」と呼んだのは、教育社会学者の竹内洋氏である。「願いましては」とそろばんを一度ご破算にするように、大学入学はそれまでの学歴や経歴を不問に付し、「下剋上」を狙えるというのである(そろばんをご破算にするということ自体、イメージがわかない世代が増えているかもしれないけれども)。
どんな家庭に生まれたとしても、高校までに学習した内容の試験さえクリアすればいい学力試験型の入試は、このご破算型選抜の典型だといえる。
しかし、年内入試はそうはいかない。推薦入試は、高校での成績や出席日数などが重要である。遅刻や欠席を繰り返し、定期テストは低空飛行だけど、一念発起していい大学に入ろうと受験勉強を始める、などということはできない。自らを律し、塾に通い、定期テストをきちんとこなし、同じ高校の中で競って大学の推薦枠を見事勝ち取る学生だけが、推薦入試に通るのである。
勤勉さの報酬が推薦入試であることを考えれば、推薦入試は高校3年間をかけた、壮大なプロジェクトであると言えるかもしれない。こうした勤勉さは、落ち着いた家庭環境と親のしつけと塾などの教育投資のたまものということも可能だろう。どんどん実質的な選抜が、早期になされるようになっているのだ。