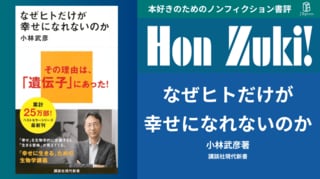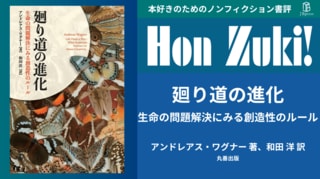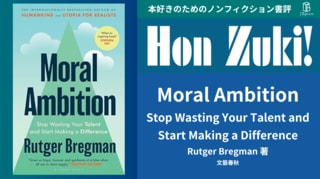ロシア工作はあったのか?
在職中に著者自身がロシア政府関係者から直接指示を受けたという記述はない。ただCAロンドン本社にロシア人の一団が現れるようになり、ロシアの新興財閥向けプレゼンに駆り出される。同僚の主任心理学者はロシアに頻繁に出張するようになり、CAが元ロシア諜報部員を雇い入れたという上司宛のメモ(真偽は不明)を見るうちに、少しずつ違和感を覚えるようになる。
親会社であるSCLとロシアの関係性に気づくのは、退職したあとのことである。(ブレグジットについては、より詳細に描かれていて、これも面白い)
ロシアにとって好都合なのは、ほとんどの西側諸国では言論の自由が保障されているということだ。言論の自由が保障されていれば、敵国のプロパガンダに同意する権利も広く認められる。言論の自由は、オンラインプロパガンダの拡散という夢をかなえてくれる魔法の杖のような存在といえる。
西側諸国における言論の自由、ソーシャルメディアの隆盛、さらに著者たちの開発した手法の組み合わせは、ロシアにとって強力な兵器のように映ったかもしれない。
「エスタブリッシュメントを粉々にする」 「革命の予言者」を自任するバノン
バノンから著者への指令第一号は、「ポリティカルコレクトネスの抑圧を感じているアメリカ人を研究してほしい」ということだった。
リベラル派エリートたちから、田舎者と揶揄されても、「ポリティカルコレクトネスを盾にされて」、何もいい返せない中部の白人男性たち。ポリティカルコレクトネスは、彼らにとって、アイデンティティーへの脅威になり得るのではないかという仮説があった。
バノンにしてみたら、典型的な民主党支持者は人種的マイノリティー支持を表明して綺麗事を並べ立てているが、そこには本当の正義とは相いれないパターナリズム(親が子どもに接するときのように他者のために良かれと思って管掌すること)がある。
いわゆる良識派が、政治的に不適切な発言に顔をしかめ、非難する。だが自身の奥深くにある差別感情や特権には気づいていない。そのような構造は、アメリカに限ったことではないのかもしれない。
バノンは「革命の予言者」を自任していたという。彼によれば、歴史上の人物の多くはアーティストだった。フランコ、ヒトラー、スターリン、毛沢東、ビン・ラディン。「社会を根本的に変えるためにはすべてぶち壊さなければなら」ず、エスタブリッシュメントを粉々にする必要がある。良識派と呼ばれる人々の思い上がり、無自覚の加害をバノンは憎んでいるようである。
ここで書かれているCAの実験結果(「人種差別を批判するほど、なおさら固執するブーメラン効果」、「たとえ貿易戦争によって雇用や利益が失われるとしても、移民グループとリベラル派を懲罰できるのであれば、怒れるアメリカ人は我慢するのではないか」、公正世界仮説と人種偏見の関連性)も興味深い。
なお、バノンの持つ思想について、著者は特にコメントしていない。ただ「バノンと私は明らかに波長が合った」とあるためか、行間から共感めいたものを感じてしまう。それは、たとえばポリティカルコレクトネスや価値観の変化に苦しむ白人男性に寄り添う視点などではなく、ただバノンという人間が描く世界観への敬意であるように感じられる。