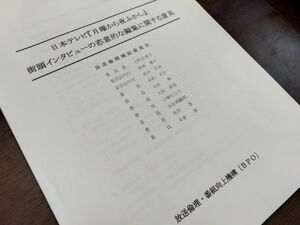垂れ流される「機能性表示食品」のCM、プロパガンダに加担するテレビ局の罪深さ
高齢者に健康の「ハルマゲドン」を突き付けるCMは見直すべきだ
岡部 隆明
ジャーナリスト
2025.6.30(月)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら