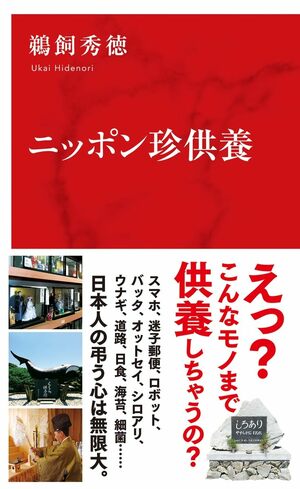数年間で何度も起こった日食に、人々は天変地異を恐れた
では、奥多摩湖畔の日食供養塔が立てられた当時、この地域では本当に日食が見られたのだろうか。
石碑には「寛政十一(一七九九)年建立、己未十一月」とある。
奥多摩地域での日食の記録を調べると、実は同年には日食は観測されていないことが分かった。
この年以前の日食を20年ほど遡ってみた。すると1786(天明6)年1月30日、当地域でほぼ金環日食に近い状態(食分99パーセント)のものが観測されている。1789(寛政元)年、1796(寛政8)年、1798(寛政10)年にも部分日食があった。
供養塔が立てられる前の数年間には、一定の頻度で日食が観測されていたようだ。
江戸時代の庶民は太陽をきちんと供養しなければ、疫病の流行や天変地異を招いてしまうのでは、と恐れたのかもしれない。
ちなみに、供養塔ができた翌年1800(寛政12)年4月1日には奥多摩地域では金環日食に近い部分日食(食分93パーセント)が観測されている。
奥多摩の人びとはこの供養塔の前で必死に手を合わせ、凶事が起きぬことを願ったに違いない。
奥多摩町にはかつて、21の寺院と33の神社があり、信仰に篤い風土であった。
路傍には地蔵や神像があちこちに置かれていたとされる。郷土芸能の一部も現代まで伝承されてきているものがあり、獅子舞や花神楽などは毎年、奉納されている。
日食供養塔を生んだ背景に、当地の豊かな精神文化があったことを言い添えておかねばなるまい。