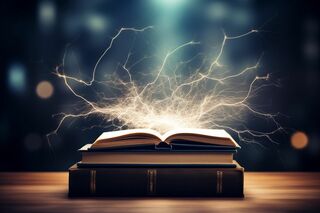生成AIで問われる大学教育のあり方
飯吉:レポートや論文の執筆に何らかの形で使っている学生は多いでしょう。ただ、生成AIに資料を読み込ませて、出力されたテキストをそのままコピペする学生は、ほとんど
残り2418文字
飯吉:レポートや論文の執筆に何らかの形で使っている学生は多いでしょう。ただ、生成AIに資料を読み込ませて、出力されたテキストをそのままコピペする学生は、ほとんど
残り2418文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら