生成AIで大学がオワコン化?巧妙化する教員vs学生のだまし合い、慶応大教員「コピペ対策」が問うた大学教育の意味
京都大学・飯吉透教授に聞く
2025.5.29(木)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

AIの活用に避けて通れない個人情報保護、世界の潮流と日本の現状
小川久仁子・個人情報保護委員会事務局審議官インタビュー(前編)
木寺 祥友

新教皇・レオ14世はなぜ「レオ」を名乗ったのか?資本主義と新技術の発展に直面したレオ13世を引き合いに出した意味
【生成AI事件簿】倫理や宗教の領域に近づくAIの活用、レオ14世はAIにどうアプローチするのか
小林 啓倫
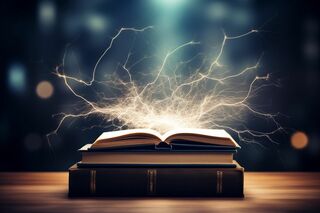
なぜ教育にAIを積極活用すべきなのか、若山牧水・北原白秋の師、尾上柴舟に見るグローバルな芸術の視線
伊東 乾

生成AIに騙される弁護士がいまだに相次ぐ――裁判に架空の判例を提出した弁護士には制裁金の勧告
【生成AI事件簿】生成AIのハルシネーションに幻惑?AIチャットボットの回答を鵜呑みにしてはならない
小林 啓倫

ゲームエンジン、AI、仮想現実…最新テクノロジーの理解には「愛」が不可欠「マシン・ラブ」展が教えてくれること
森美術館にて展覧会「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」が開幕
川岸 徹
本日の新着
ニュース・経営 バックナンバー

「1円でも稼げる仕組みを作れ」ANAの執念、3400件の新規事業案と“二刀流人材”を生み出す「がっつり広場」の舞台裏
堀尾 大悟

守り中心のCISOではもう限界、日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会代表理事が唱える「CISO2.0」の役割
前川 聡

人手不足でタクシー業界は倒産急増 テスラ、バイドゥが開発する「ロボタクシー」が救世主となるための条件とは?
雨宮 寛二

ハリウッドが迎えた容赦ない最終局面…“映画のど素人”とネットフリックスが引き起こした「配信革命」の帰結
アンドリュー・マカフィー | 小川 敏子

「あらゆる上場企業がいつ標的になってもおかしくない」増加する「同意なき買収」、狙われる企業の特徴と防衛策は?
ボストン コンサルティング グループ | 加来 一郎 | 坂上 隆二

◆再配信◆藤本隆宏教授、一橋大・楠木建氏、IHI・エグゼクティブフェローらが再登場!製造DXの最前線を探る
JBpressセミナー事務局







