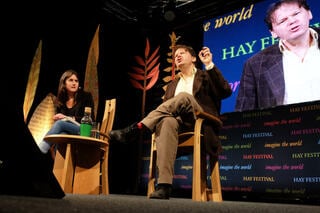クラウド領主と封臣、農奴の関係
大澤:封建制では、土地を持つ封建領主がいて、その下に領主に従う家臣がいて、さらにその下には農奴(農耕する奴隷)がいます。農奴は働かされて、あがりを家臣に納め、家
残り4459文字
大澤:封建制では、土地を持つ封建領主がいて、その下に領主に従う家臣がいて、さらにその下には農奴(農耕する奴隷)がいます。農奴は働かされて、あがりを家臣に納め、家
残り4459文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら