資本主義の王者が構築したテクノ封建制の監獄、私たちクラウド農奴はGAFAMなどのクラウド領主に対抗できるのか?
【大澤真幸が語るこの一冊】バルファキスの『テクノ封建制』が描く資本主義の終わりとその後の世界
2025.5.21(水)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
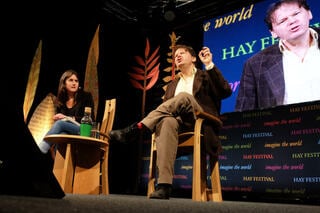
「そもそも農業革命など存在しなかった」、人類学者・デヴィッド・グレーバーの巨大な遺言をどう読むか
大澤真幸が読み解く『万物の黎明 人類史を根本からくつがえす』と、農業革命という幻想
長野 光

哲学から量子力学の謎に迫る「エージェンシャル・リアリズム」とは何か、大澤真幸がカレン・バラッドを読み解く
『宇宙の途上で出会う 量子物理学からみる物質と意味のもつれ』が語る、物質・空間・時間はいつ生み出されるのか
長野 光

宗教的な感覚や神の概念を人間が共有するのはなぜか?社会学者・大澤真幸が語る「1.5人称的な感覚」
【プロが語るこの一冊】宗教の発生を進化の理論で説明した『宗教の起源 私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか』
長野 光

AI開発競争で表出した超人思想、ニーチェは『ツァラトゥストラはこう言った』で何を語ろうとしたのか?
『ニーチェ 哲学的生を生きる』の森一郎が語る、ニーチェの超人思想が意味するもの
長野 光 | 森 一郎

現代思想界の長老、チョムスキーとハーバーマスがウクライナ戦争と停戦を巡る議論で陥った思想的な罠
【著者に聞く】『悪が勝つのか?』の井上達夫が語る②、ウクライナ戦争に世界が対応できない理由
長野 光 | 井上 達彦
本日の新着

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影
生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に
小久保 重信

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙
木村 正人

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか
【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略
小林 啓倫

トランプは本気でグリーンランドを欲しがっている、国内の不満を国外の成果で癒す米国大統領
Financial Times
地球の明日 バックナンバー

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか
小林 啓倫

フードデリバリーの不正行為というデマが広まったのはなぜか?3600万回以上のスクショが拡散された複合的な構図
小林 啓倫

YouTubeショートの3分の1が脳を腐らせるゴミ動画、AI生成の動画で億単位のカネが儲かる今の仕組みはおかしくない?
小林 啓倫

生物に影響を与える繁殖干渉とは?種を超えたオスの求愛が相手種を絶滅させる
岸 茂樹

【AIの人間観】争いや戦争など人間の「愚行の歴史」を学び続けるAIは人間をどのような存在として認識しているのか?
榎並 利博

世界史がめったに教えないソクラテス、プラトンの性的指向
市川 蛇蔵



