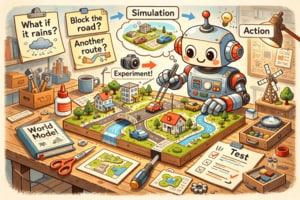ChatGPTの予測能力を爆上げするプロンプトが判明、「物語プロンプト」とはいったい何か?
【生成AI事件簿】ロシアによるウクライナ戦争の帰趨についても驚きの回答が
小林 啓倫
経営コンサルタント
2025.3.23(日)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら