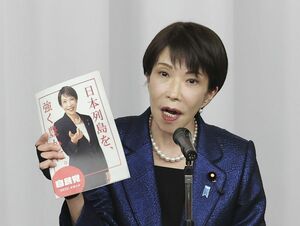2019年7月の都市対抗野球で王子に勝利し、喜ぶ日本製鉄鹿島ナイン(写真:共同通信社)
2019年7月の都市対抗野球で王子に勝利し、喜ぶ日本製鉄鹿島ナイン(写真:共同通信社)
プロ野球の監督交代のような大きな話題になることはなかったが、アマチュア野球界に、昨年のシーズン限りでユニフォームを脱いだ3人のベテラン監督がいた。高校、大学、社会人とそれぞれのカテゴリーで実績を残してきた昭和の匂い漂う無骨な野球人たちは、平成、令和と変わりゆく時代の中で、どんなふうに選手と向き合い、チームを作ってきたのだろうか。(矢崎良一:フリージャーナリスト)
一人目は、日本製鉄鹿島の中島彰一(前)監督。古くからの高校野球ファンであれば、その名前を聞いてピンと来る人は多いだろう。
1984年夏の甲子園。変幻自在の采配で「木内マジック」と呼ばれた当時53歳の木内幸男監督率いる取手二高(茨城)は、エース石田文樹(元・横浜)や主将の吉田剛(元・阪神)らの活躍で勝ち進み、決勝戦で桑田真澄・清原和博の「KKコンビ」を擁するPL学園(大阪)と対戦。大方の予想を覆して優勝候補のPLを撃破し、初優勝を果たした。
この試合の延長10回表、桑田から試合を決める決勝3ランを打ったのが、取手二の「5番・キャッチャー」中島だった。
中島は高校卒業後、東洋大、住友金属鹿島(現・日本製鉄鹿島)でプレーを続け、96年に選手を引退した。その後、鹿島でコーチ、マネージャーを歴任し、2002年に監督に就任する。08年に一度は退任し社業に就いていたが、再び監督を任された16年以来、昨年まで9年間、チームの指揮を執ってきた。
退任を公にしたのは、昨シーズンの最後の公式戦となる11月の日本選手権(京セラドーム大阪)の開幕直前。大阪入りした翌日、練習の後に選手たちを集め、「今年でやめることになりました」と伝えた。
「早く伝えてあげなきゃ、と思っていたんですよ」と申し訳なさそうに言う。後任の人事を含め水面下で引き継ぎは進めていたが、会社内での承認が完全におりるまで発表は待つようにと指示を受けていたため、選手にはギリギリまで話すことができなかった。
「みんな薄々わかっていたと思いますよ」と中島は言うが、動揺は大きかった。「一瞬でも、1試合でも長く、一緒に野球をやらせてくれ」という言葉を聞き、その場で涙を流す者もいたという。
島田直人マネージャーが密かにメーカーに発注していた中島の背番号「66」の刺繍が入った青のリストバンドが配られ、選手、スタッフは全員それを着用して試合に臨んだ。「66」は中島の生まれた年(1966年)から取ったものだ。
「そこまでしなくていいよ、ってちょっと照れくさかったけどね。でも、それがみんなの合い言葉みたいになって、チームが勝つための武器になってくれるんだったらいいのかなと思って」