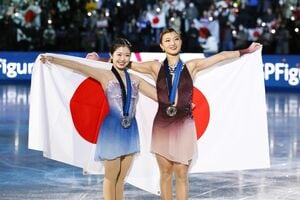野球肘検診を見守る古島弘三医師(筆者撮影)
野球肘検診を見守る古島弘三医師(筆者撮影)
全国に広がる「野球肘検診」
秋から冬、野球のシーズンオフに当たるこの時期、少年野球では全国的に「野球肘検診」が実施される。
少年野球の世代から投げ込みなど過度の投球練習をすると、肘や肩を故障することは、1970年代にはわかっていた。徳島大学の整形外科医が、県内の野球少年を検診して、多くの子供が障害を負っていることが明らかになった。医師たちはこの時代から警鐘を鳴らしていたが、少年野球指導者がこれに反応することはほとんどなかった。
特に深刻なのは「野球肘」だ。中学生以下の子供の「野球肘」には、大きく分けて2つある。
「上腕骨内側上顆障害」は「リトルリーグ肘」とも言われる。肘の内側が痛む、肘の運動障害などがみられるが、一定期間ノースロー状態をキープするとともに、フォームを改善するなどすれば、回復する可能性が高い。
しかし肘の外側が痛くなる「離断性骨軟骨炎」は、はるかに厄介だ。肘の曲がる部分の軟骨を痛めてしまうタイプの障害で、多くが小学校の時に発生する。軽症の場合は一定期間ノースローにすることで回復するが、悪化すると手術せざるを得なくなる。完全治癒しないと肘の変形や曲げ伸ばしの障害へと進行し、選手の将来を左右しかねない。
ちなみに高校生以上では、「内側側副靱帯損傷」という中学生以下とは異なる肘の障害が顕在化する。悪化すると、靱帯再建手術、いわゆるトミー・ジョン手術をすることになる。中学時代に「離断性骨軟骨炎」を発症し、完治しないまま高校に進んだ選手は、高校でこの障害を負うことが多いと言われる。