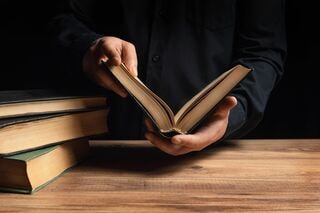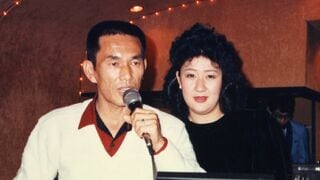藝大入学後に遭遇する苦悩
その入試倍率の高さから、藝大には天才的な人間だけが行くところだという錯覚は、受験生でさえ持ってしまいがちなことである。しかしこれは幻想だ。一見才能溢れる人物も
残り1105文字
その入試倍率の高さから、藝大には天才的な人間だけが行くところだという錯覚は、受験生でさえ持ってしまいがちなことである。しかしこれは幻想だ。一見才能溢れる人物も
残り1105文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
『薬屋のひとりごと』架空の国の後宮を舞台に、薬師の拗らせ女子が次々と謎を解き明かす極上のミステリー