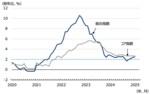トランプの前に詰みつつあるEU、米国の要求通り防衛費の積み増しを進めれば、インフレ再燃で有権者の怒りも沸騰か
【土田陽介のユーラシアモニター】財政ルールを緩和しても立ちふさがるハードル、前門のトランプ、後門のインフレ
2025.2.24(月)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
ルール形成をテコに国際政治をリードしようとしたEUの戦略に赤信号、高インフレ・競争力低下・トランプの三重苦

あわせてお読みください

【2024年を振り返る・ドイツ編】政情不安・景気低迷・産業空洞化の三重苦に直面するドイツ、もはやディストピアか
【土田陽介のユーラシアモニター】フォルクスワーゲンも罹患、深刻化するドイツ経済の本当の病巣
土田 陽介

GDPで日本を抜いたドイツで吹き荒れるリストラの嵐、ドイツ経済で何が起きているのか?
2024年を振り返る:【土田陽介のユーラシアモニター】過去10年で最多となる見込みの失業者数と働かなくなったドイツ人【JBpressセレクション】
土田 陽介

前年比4.1%と実質GDPは上振れしたのにドルベースの輸入が落ち込んでいるロシア、果たして経済は好調と言えるのか?
【土田陽介のユーラシアモニター】2月以降、急速に進むルーブル高が示唆すること
土田 陽介

なぜ化石燃料の「脱ロシア化」を進めるEUはロシア産LNGの輸入を続けているのか?
【土田陽介のユーラシアモニター】天然ガスの輸送を打ち切ったウクライナだが、EUはロシア産の輸入を止める気ゼロ
土田 陽介

【2025年を読む】2026年の経済成長率は約6%!独仏の経済減速が深刻なEUで浮上するウクライナ復興需要の皮算用
【土田陽介のユーラシアモニター】戦時経済化が進むウクライナ、ロシアとあまりに対照的な経済情勢の要因
土田 陽介
本日の新着

日本円がいまだにこれほど安いのはなぜか?
The Economist

金暴落を招いた「ウォーシュ・ショック」は炭鉱のカナリアか…金から金融市場全体に“バブル崩壊”が波及する危険性
藤 和彦

【どうなる衆院選】参政党だけじゃない、バズりが政治を動かす危険…SNS選挙と解散常態化で日本はヤバイ国に
【マライ・メントラインの世界はどうなる】作家・評論家の古谷経衡氏に聞く(後編)
マライ・メントライン | 古谷 経衡

【誰のための経済政策か】極端な政策で泣くのはいつも生活者、歪みは常に「弱いところ」へ流れ着く
市場主義は成長を生み出すが格差を拡大させ、国家主義は一時的な安定をもたらすものの活力低下と経済の歪みにつながる
平山 賢一
USA バックナンバー

「私はドルをヨーヨーのように上げたり下げたりできる」トランプ発言に透けて見える「プラザ合意」再現の傲慢な野望
木村 正人

トランプ新戦略から「台湾」の文言が消えた不気味な理由、元自衛艦隊司令官が読み解く「だんまり戦術」の正体
木村 正人

中国封じ込めの“裏庭固め”へ──加速するトランプ流「ドンロー主義」、グリーンランドの次に標的となる国はどこか
深川 孝行

米国はもう守らない?トランプ新戦略が日本に迫る「防衛費GDP5%」と自立、慶大・北川敬三教授が警告する未来
木村 正人

中国に軍事力の違いを見せつけた米国の対ベネズエラ作戦、トランプ大統領のもう1つの狙いは「台湾侵攻抑止」か
深川 孝行

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙
木村 正人