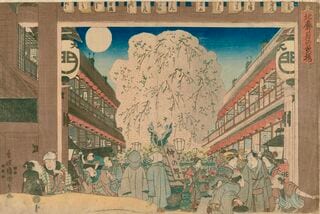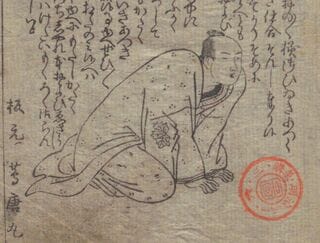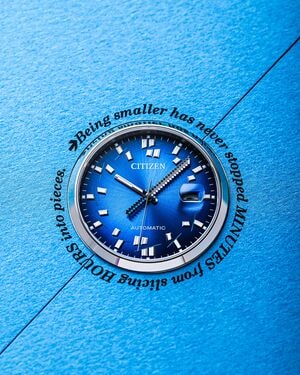旧江戸城の田安門 写真/Gengorou/イメージマート
旧江戸城の田安門 写真/Gengorou/イメージマート
(鷹橋忍:ライター)
大河ドラマ『べらぼう』では、「御三卿」と称される、寺田心が演じる田安賢丸(松平定信)、生田斗真が演じる一橋治済(ひとつばしはるさだ)、落合モトキが演じる清水重好(しみずしげよし)などが登場する。徳川御三家に比べ、御三卿は少し馴染みが薄いのではないだろうか。そこで、今回は御三卿を中心に取り上げたい。
御三家とは
御三卿の前に、まず御三家の復習をしておこう。
御三家は、徳川家康の九男・徳川義直(よしなお)を祖とする「尾張徳川家」。
十男・徳川頼宣(よりのぶ)を祖とする「紀伊徳川家」。
十一男・徳川頼房(よりふさ)を祖とする「水戸徳川家」の三家を指す。
御三家はそれぞれ、尾張家が六十一万九千五百石、紀伊家が五十五万五千石、水戸家が二十八万石の独立した大名である。
将軍継承権を有し、徳川姓を称することが許されていた。
家康は、将軍家に跡継ぎがいなくなった場合の控えとして、御三家を立てたという(歴史読本編集部編『徳川将軍家・御三家・御三卿のすべて』所収 山本博文「Q&A 将軍家・御三家・御三卿の基礎知識」)。
家康の危惧は、現実となる。
七代将軍・徳川家継の死により将軍宗家の血脈が途絶え、紀伊徳川家の徳川吉宗が、御三家からはじめて、将軍の座に就いた。
八代将軍となった吉宗の血筋から、御三卿が生まれることになる。
御三卿の由来は?
御三卿とは、吉宗の次男・宗武(むねたけ)を祖とする「田安家」。
四男・宗尹(むねただ)を祖とする「一橋家」。
九代将軍・徳川家重(吉宗の長男)の次男・重好(しげよし)を祖とする「清水家」のことである。
従三位以上の官位をもつ者を「公卿」と呼ぶが、御三卿の「卿」は、宗武も宗尹も重好も、初叙が従三位であったことに由来するという(大石学編著『図説 江戸幕府』所収 行田健晃「御三卿――柔軟に将軍を支えた「城住み」の徳川一門」)。
御三卿は将軍の一族であり、家格は御三家に次ぐとされるが(教育社編『日本史重要姓氏辞典』)、城持ちではなく、江戸城の郭内に居を構えた。
御三家が独立した大名であるのに対し、御三卿は「将軍家に附属し、養われる存在」で、独立性に乏しかったといわれる。