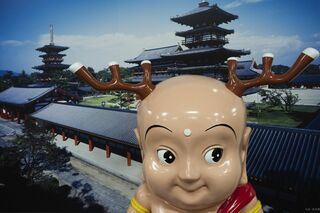「ポスト資本主義社会の具現化」が意味するところ
これまで里山や里海といったローカルコモンズは地域の共通資本として適切に管理されてきた。里山や里海の生物多様性が高いのは、自然の恵みを持続可能とするため、人間が
残り2610文字
これまで里山や里海といったローカルコモンズは地域の共通資本として適切に管理されてきた。里山や里海の生物多様性が高いのは、自然の恵みを持続可能とするため、人間が
残り2610文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら