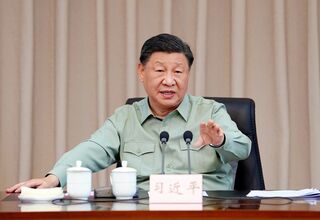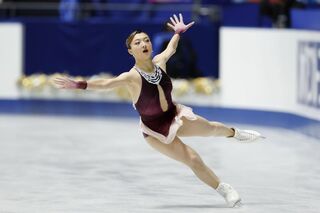宝塚歌劇団を鉄道の多角化事業に組み入れた名経営者、小林一三の軌跡をたどる
小林生誕150年の節目に揺れたタカラヅカと、岐路に立つ鉄道のビジネスモデル
2024.1.12(金)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

ローカル線・近江鉄道“ズレ、ズレ、ズレ”でも決裂せず…迎えた運命の2024年
【近江鉄道線血風録⑨】いよいよこの春「上下分離」へ、破談を回避したカギは
土井 勉

地域鉄道の96%が赤字…コロナ後のローカル線にいったい何が起きているのか?
【近江鉄道「血風録」①】コストカット・内部補助は限界に、加速する存廃議論
土井 勉

15年前の「宝塚音楽学校いじめ事件」、追及できなかった記者の悔恨(1)
「いじめの事実はない」とする宝塚の体質、なにも変わっていなかった
神宮寺 慎之介

15年前の「宝塚音楽学校いじめ事件」、追及できなかった記者の悔恨(2)
万引きの濡れ衣で退学処分、不誠実な対応で少女の夢を断ち切った学校
神宮寺 慎之介

小田急“白いロマンスカー”の完全引退で鮮明になった「通勤特急へのシフト」
最高レベルの技術やサービスを盛り込んだ「50000形VSE」が短命だったワケ
小川 裕夫
本日の新着
注目のひと バックナンバー

サントリー会長を辞任した新浪剛史氏、日本を代表する実績抜群の「プロ経営者」にこの先どんな道が待っているのか
関 慎夫

JAL倒産の修羅場から再生までを仕切った歴戦の「倒産弁護士」、その手腕と日本社会への提言
大西 康之

中学で直面した男女のフィジカル差、マネジャー転身で得た財産、野球用品商社の営業で活躍する女性が辿り着いた役割
佐伯 要

サントリー会長を辞任した新浪剛史氏、日本を代表する実績抜群の「プロ経営者」にこの先どんな道が待っているのか
関 慎夫

選手の血糖値を測定してメンタルを可視化する、ラ・サール高校、東大の野球部で培った研究者魂と起業家精神
佐伯 要

【イーロン・マスクの源流④】「平穏な日が続くといらだつんです」、ツイッター買収前のマスク氏の精神状態
ウォルター・アイザックソン