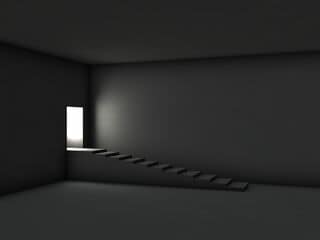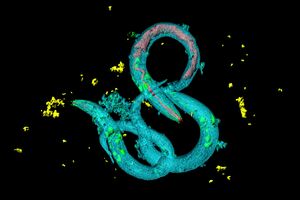「2001年宇宙の旅」で既に描かれていた技術
米持:音声対話技術の難易度が高い理由は、たくさんあります。「音声認識技術」と「言葉の理解・処理技術」の研究開発が別々に行われていることは、大きな要因の一つと言え
残り4415文字
米持:音声対話技術の難易度が高い理由は、たくさんあります。「音声認識技術」と「言葉の理解・処理技術」の研究開発が別々に行われていることは、大きな要因の一つと言え
残り4415文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら