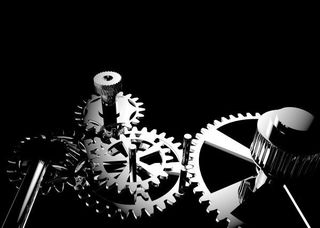MRI搭載車利用の脳ドックを実現した官民連携
三重県東員町の水谷町長インタビュー 前編
2022.2.21(月)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
本日の新着

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか
【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略
小林 啓倫

トランプは本気でグリーンランドを欲しがっている、国内の不満を国外の成果で癒す米国大統領
Financial Times

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②
町田 明広

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く
【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか
菅原 淳一
地域を元気に バックナンバー

【旧北陸線トンネル群】鉄道廃線トンネル“西の横綱”、保存状況良好で今も地域インフラとして活躍中
花田 欣也

“撮り鉄”を巡るトラブル続発、私有地侵入・路上駐車・ゴミのポイ捨て…鉄道会社や沿線住民との共存は図れないのか
小川 裕夫

明治の煉瓦のトンネルを「森のビアホール」に! 愛知県春日井市の愛岐トンネル群で次々生まれるユニークなアイデア
花田 欣也

鉄道の衰退は人災だった、SLを走らせて「昭和の汽車旅」と言ってももはや通用しない
池口 英司

福島県相馬市のビーチバレー大会はなぜ地域を巻き込んだイベントになったのか?地域活性化へのスポーツの生かし方
桑本 香梨 | 笠原 千尋

北広島の「どん北」は、なぜこんなにも地元で愛されるのか?地域を盛り上げるスポーツの力
桑本 香梨 | 笠原 千尋