大企業社員「テレワーク、めっちゃしんどい」の現実
あなたの会社の社長がテレワークを拒む理由とは?
2021.7.4(日)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
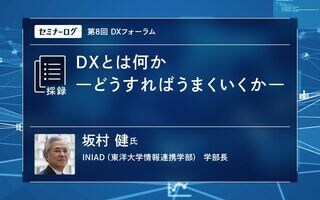
DXとは何か ―どうすればうまくいくか―
坂村健氏が語る、今すべきことと日本の未来
坂村 健(INIAD学部長)

PMの現場からひもとく、コミュニケーションの最適バランス
対面か? オンラインか? 重要なのはそのバランスだ!
マネジメントソリューションズ

ジョブ型雇用の進展で企業の盛衰を分けるものとは
「複業」の時代、人々はミッションの有無で企業を選ぶように
PublicLab編集部

ニューノーマル時代に求められる企業の健康管理改革
コロナ禍の重要課題、メンタルヘルス対策もCarelyが解決する
JBpress

鼎談「経営企画はいかに企業へと貢献すべきか」
生産性向上に向けた役割と今、すべきこととは
JBpress
働き方と教育 バックナンバー
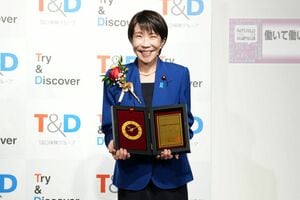
モーレツに働き続ける高市政権の誕生で女性活躍は進むのか?両極端に転び得る「2つのシナリオ」
川上 敬太郎

上司からの連絡に邪魔されず休日を穏やかに過ごすには、「つながらない権利」より「レスポンス主導権」の確保が必要
川上 敬太郎

消えゆく「役職定年」、年齢による強制的な降格と減給の仕組みとはなんだったのか
フロントラインプレス

それでも退職代行・引き止めサービスが活況を呈する背景と問題点、会社と社員の意思疎通はなぜ壊れるのか
川上 敬太郎

メンタルダウンから復活、元アパレルマーチャンダイザーがついに「手触りのある実感」を得られた仕事とは
韓光勲

高市発言で今も物議を醸す「ワークライフバランス」の意義、労働時間規制の緩和は「長時間労働の推奨」につながるか
川上 敬太郎



