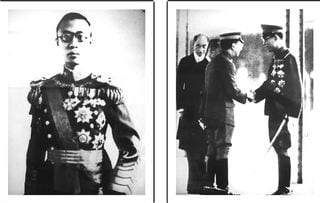1937年(昭和12年)に竣工した三越百貨店大連支店は大連駅からも近い連鎖街とは道路を挟んだ向かい側の旧常磐町にある。三越はよく知られているように日本の百貨店の元祖。5階建てで4階はレストランになっていた。戦後はソ連軍に接収された後に大連市に返還され、ロシア系の百貨店である秋林(チューリン)女店として使われたが、2016年にZARAという店舗に変わった。
1937年(昭和12年)に竣工した三越百貨店大連支店は大連駅からも近い連鎖街とは道路を挟んだ向かい側の旧常磐町にある。三越はよく知られているように日本の百貨店の元祖。5階建てで4階はレストランになっていた。戦後はソ連軍に接収された後に大連市に返還され、ロシア系の百貨店である秋林(チューリン)女店として使われたが、2016年にZARAという店舗に変わった。拡大画像表示
◎【写真特集】「消滅国家、満洲国の痕跡を求めて」 記事一覧はこちら
(文+写真:船尾 修/写真家)
≪かつての日本の植民地の中でおそらく最も美しい都会であったにちがいない大連を、もう一度見たいかと尋ねられたら、彼は長い間ためらった後で、首を静かに横に振るだろう。見たくないのではない。見ることが不安なのである。≫
という書き出しではじまる『アカシヤの大連』は、満洲・大連生まれの詩人で作家の清岡卓行の私小説だ。彼はこの初めての小説で1970年(昭和45年)度の芥川賞を受賞している。
1922年(大正11年)に日本の租借地である大連で生まれた清岡は大連一中を卒業すると単身日本へ渡り、東京帝国大学仏文科に進む。しかし戦争が激しさを増した1945年(昭和20年)春の東京大空襲の直後、実家のある大連へ戻った。
≪大連の五月は、彼にとって五年ぶりのものであったが、こんなに素晴らしいものであったのかと、幼年時代や少年時代には意識してなかったその美しさに、彼はほとんど驚いていた。≫
10万人が死亡し、100万人が罹災したといわれる3月10日の東京大空襲。食料はとっくの昔に配給制となっており、清岡に限らず都会に暮らす人たちはみな飢えていた。しかし大連へ戻ってくると、拍子抜けするほどそこには戦争の影などなく、喉から手が出るほど欲した米や肉や卵など食べるものはなんでも手に入った。酒も煙草も入手に困らない別天地だった。彼は毎日、昼ごろに起き、アカシヤの花の甘く芳しい香りを嗅ぎながら散歩し、6畳の自室にこもってレコードを聴いたり読書をしたりしてゆったりと過ごした。
宙ぶらりんの存在だった大連
ただ、自分が何者であるのかという問いはずっと心の内に澱のように溜まっていた。戦後、清岡が文学の道へと進んだのは、おそらくその問いから彼自身が逃れられなかったからではないだろうか。それは、植民地が自分の故郷であるということへの葛藤である。
≪彼は、自分が日本の植民地である大連の一角にふるさとを感じているということに、なぜか引け目を覚えていた。・・・自分が大連の町に切なく感じているものは、主観的にはどんなに〔真実のふるさと〕であるとしても、客観的には〔にせのふるさと〕ということになるのかもしれないと思った。≫