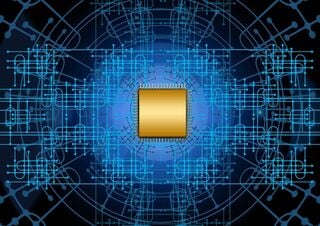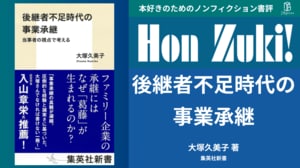(写真はイメージです)
(写真はイメージです)
日本陸上界のスター「ストロング・クレイジー」は、和歌山の農家で生まれ育った。高校のインターハイにはアフロパーマで出場。いつもタバコをふかし、酒も毎晩ボトル1本。朝方まで女を抱いた後、日本選手権で優勝。そして幻にされた世界新記録――ノンフィクション作家の上原善広氏は、そんな「溝口のやり」を忘れられず18年以上も取材し続けた。溝口和洋氏の一人称で綴った執念のノンフィクション。(JBpress)
(※)本稿は『一投に賭ける 溝口和洋、最後の無頼派アスリート』(上原善広著、角川文庫)より一部抜粋・再編集したものです。
私は大学生になってやり投げのために生きることを決意したときから、日常生活も含め、すべてをやり投げに結び付けてきた。箸の上げ下ろしから歩き方まで、極端にいえばセックスをしている最中でも、この動きをやり投げに応用できないかと考え続けてきた。
45歳で農業を継ぐまで、私はやり投げ選手だったこともあるし、コーチをしていたこともあるし、パチプロとして生計を立てていたこともある。結局のところ、農業もパチプロも、根底はやり投げと共通している。
もちろん農業には農業の厳しさがある。
しかし、ついやり投げとつなげて考えてしまう。15で始めたときからこれまで、やり投げのことしか考えてこなかったのだ。自らの前半生を賭けたやり投げは、もはや私の思考の基礎となっている。
しかしいま、私の手元には、やり投げに関するものが何もない。
トロフィーも表彰状も、何もない。
その代わり、私には、鮮明な記憶だけが残っている。
何年の何月何日、どの試合の、何頭目が何m何㎝で何位だったか、今でも瞬時にそれを思い出すことができる。
それ以上の勲章があるだろうか。