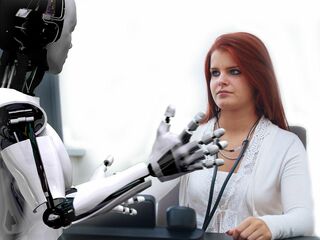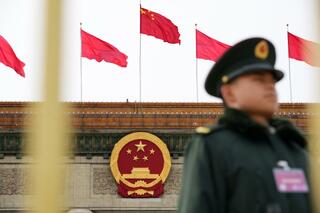「手を引っ込めた」意味
安楽死審査委員会が作成した安楽死の『実施手引書』には以下のように記載されている。
「(4.4)認知症の患者 安楽死は、書面による意思表明書に指示・明記された状況となったその時点で、安楽死実行が受諾されうるものとなる。ただし、その直前に、対立する兆候(生命終結を欲していないといったはっきりしたサインを患者が呈した)がなかった場合に限る。さらに、患者は耐えがたい苦痛を経験していると明らかに見て取れる場合である。先に述べたように、意思表明書の内容を判断することが重要な役割を果たす」
そこで問題となるのは、医師が患者の意思表明書の作成に当たり、事前に患者とのコミュニケーションを行う努力をしなかったので、この動きがいったい何を意味するのかについて医師は明確に説明することができなかった点である。痛みに対する反射的反応なのか、それとも安楽死が行われていることを理解して、それから逃れる動きであったのか、あるいは単に注射が嫌だっただけなのか、それらの点を医師は説明できなかった。
安楽死実行時に注射が痛くて手を引っ込めることはありえる。しかし、事前にしっかり申し合わせがあったのだったら、安楽死実行を継続する理由となる。しかし、事前に全く話し合いがなかったのだったら、手を引っ込めた際に一旦中止すべきだった、そこでじっくり考えなければならなかった、ということである 。
福生病院透析中止事件
以上のオランダ初の安楽死訴追事件を念頭に置いて、日本の福生病院の透析中止の事件を考えてみよう。
福生病院事件とは今年の3月から4月にかけて新聞紙上を賑わした事件で、昨年8月に起こった事件である。腎臓病患者の40代女性が、人工透析治療をやめた後に、死亡した事件である。
新聞等の報道によると、長い間透析治療を受けてきて、透析専用の血液の出入り口が閉塞した腎臓病の40代患者が、福生病院を訪れ、医師に治療について相談した。医師は首周辺から管を入れる透析方法を提案した一方、生死に直結する危険性があるとの説明と併せて透析をしない選択肢も示したとのことである。女性は夫とともに説明を受けた上で、「透析はもういや」と透析を受けない意思確認文書に署名し、8月14日に入院し、同16日に死亡した事件である。
ただし、死の当日の未明に、「透析中止の撤回の意思」を看護師に示していたことが看護師の記録に残っているという。しかしその後症状が落ち着き、再度医師が意思確認を行ったところ、「苦痛を和らげる」治療を望んだとのことである。
福生病院の医師は、「患者の意思を尊重した」といっている。確かに「患者の意思を尊重する」というのは、1970年代にアメリカで誕生したバイオエシックスの基本的考え方で、専門家である医師ないし医療者が患者に代わって決めるという、ともすれば患者の意思を無視しがちな旧来の医の倫理(これをパターナリズムという)に対抗する考え方であり、それ自体は大切なことである。
問題は、オランダの事件でも問われているように、患者の意思の確認の仕方である。しかも意思確認が、「苦痛の軽減か、それとも透析の再開か」という二者択一になっている点である。
①新聞報道によると、外科医は「正気な時の(治療中止という女性の)固い意思に重きを置いた」と説明しているという。また、病院は「透析離脱の証明書」をとったとも述べている。しかし、一度文章で確認書を提出しているとしても、その意思が永遠に効力を持つのではないことはオランダの事件からも明らかである。「撤回の自由」があるのだから、絶えず新しい意思確認が必要なのだ。
それではころころ変わる患者の意思表示のどの意思を尊重したらいいのかと医療者は戸惑うかもしれない。そこで文書で書いたもののみが効力を有すると捉えたとするなら、それはあまりにも形式にこだわりすぎているといえる。
確かにオデュッセウスのように、人はセイレーンの声に惑わされることもあるかも知れない。しかしオデュッセウスは、はじめに「惑わされないように」と頼んでおいたではないか。耳栓をして絶対に私の声を聞かないようにと。そのような付帯事項が明確に示されていなければ、いつでも撤回可能と判断すべきである。たとえその選択が、良い結果を生まない可能性が高いとしても、だ。
逆に言えば、医師と患者は意思表示書を作成する場合には、その点まで考えて明確に記載しておく必要がある。そうでなければ、その都度の患者の意思の確認を絶えず怠らないことである。