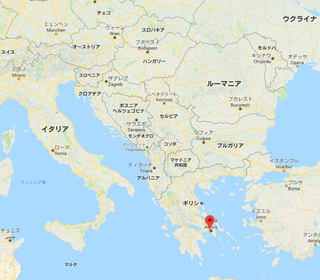筆者のフランス取材の経験から他にもいくつかの要因が考えられる。
例えば、中国研究に従事する専門家の多くは左派に属し、容共的ですらある。共産党が支配する中国に一定の親近感を抱く人は少なくない。かつての最高指導者・鄧小平がフランスへ留学した歴史も関係しているのか。もっともこの傾向は欧州以外でも見られる。対中関係に関する議論を主導する立場にあり、「中国も豊かになれば将来は民主化するのではないか」との夢すら抱
遠いアジアの安全保障情勢は、欧州ではニュースになりにくく、一般国民が関心を持つこともほと
もちろん外交当局やEUの次元では、中国を安全保障の文脈でとらえる視点も存在はする。トランプ政権が「離脱」したイランの核開発をめぐる多国間合意には、EUやロシアと並び、国連安保理の常任理事国である中国が合意当事国として関与した。中国海軍はアデン湾では海賊対策に参加し、各地の国連平和維持活動(PKO)にも積極参加しているからだ。
一方、欧州の対中経済関係が深まった結果、中国を安保上の脅威と位置づける議論が軍需産業を含む財界にとっては面倒なものとなる一面は否めないだろう。
浮沈をかけた改革はなるか?
こうした背景を踏まえると、マクロン氏がストレートな物言いで習氏の面前でその野心をけん制し、EU首脳会議でも新たな対中戦略を採択した事実の重みが分かるだろう。欧州は今や、世界で覇権を競う米中の競争力やロシアの複合的な脅威を前に、強力なプレーヤーたちに“捕食されかねない”という弱者としての危機感を抱いているのだ。
問題の一因は、EU加盟国が自国の国家安全保障政策に関する主権をまだEUに移譲していない制度にもあろう。例えば、中国の通信大手「華為技術(ファーウェイ)」を5G通信網整備に関与させるか否かについての最終的な判断は、EUではなく、加盟国が下す。安保政策の「統合不足」は、中国による分断工作を許す弱点だろう。マクロン氏が中国に注文をつける一方で、30
マクロン氏はさる3月5日、EU加盟国の28のメディアに寄稿し、「欧州の再生」を呼びかけた。ドイツを怒らせるユーロ圏の共通予算構想など従来の主張は封印し、米国が強く求める国防費の増額をEUが義務化することや、内実の伴う共同防衛計画の策定、EUから離脱するであろう英国を取り込んだ「欧州安全保障理事会」の創設、相互防衛条約の締結をなど提唱した。通商政策では、租税、データ保護、環境などのEU基準や戦略的利益を無視した商取引を禁じることや、米中並みの産業・調達政策を導入すべきことも主張した。
EUが今後、マクロン氏の問題提起をどこまで議論するかは不透明だ。28カ国の総意で重要案件を決めていくEUの意思決定は確かに時間がかかる。だが、こうした大手術が必要であることは間違いない。第2次大戦後の欧州は「平和構築」「繁栄の共有」「民主制度の改革」という発展指向の試みによって運命共同体を築いた。その欧州はいま、文明を共有する一体的な空間の「防衛」、つまり自らの浮沈をかけた闘いに直面している。