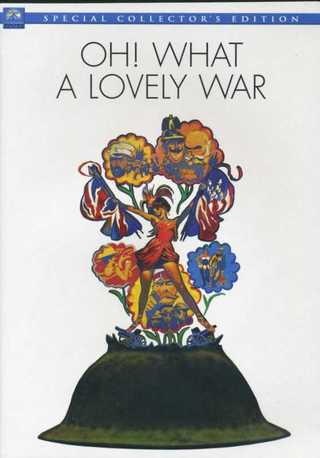リミニのフェリーニ広場
リミニのフェリーニ広場
昨年11月他界したベルナルド・ベルトルッチ監督を追悼して、これまで3回にわたりその作品を紹介してきた。そこには様々な「過去」との対話があった。
前回紹介したエルマンノ・オルミ監督やタヴィアーニ兄弟など、多くのイタリア人映画作家も、ベルトルッチ同様、自身の、祖先の、母国の「過去」を映しこんだ作品を残してきている。
特にベルトルッチが、『暗殺の森』(1970)など、繰り返しテーマとしているファシズムは、イタリア人の「過去」の深い傷であり、問いが尽きることはない。
『ラストタンゴ・イン・パリ』(1972)の「成功」により、時間も予算もふんだんに、「完成」した長編『1900年』(1976)は、そうした「過去」を後世に伝えようという映画作家としての使命さえ感じさせる歴史絵巻である。
20世紀の始まる1901年の同じ日に同じ農場で生まれた農場主の孫アルフレードと農夫の孫オルモの物語は、階級を超えた友情を軸に、農民の貧困、労働闘争、共産主義の浸透、さらには第1次世界大戦、と、時代は移り、ラスト、ファシズムの萌芽を示し、その第1部が幕を閉じた。(→前回コラムで詳述)
そして始まる第2部は、新しい農場管理人である「黒シャツ隊」のファシスト、アッティラがもう1人のキーパーソンとなり、民衆の中の「ファシズムの興亡」が描かれていく。
アルフレードと新妻アーダの結婚式がブルジョワの招待客集まるなか豪勢に行われている
別の部屋に集う農夫たちも 華やかさはないがアルフレードを祝福する
招待客の会話のなかから 黒シャツ隊の面々の得意げな話声が聞こえてくる
「フェラーラの同志と合流した時は涙が出た」
「歴史をつくるのだと実感した」
「行先は? ローマだ ローマ進軍だ!」