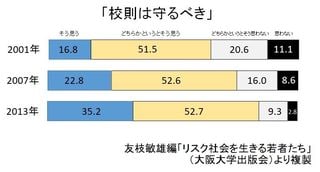田舎暮らしは楽園か
あるテレビ局の番組に「○○の楽園」というのがある。還暦前後の夫妻が田舎に移住し、これまでの仕事とはまったく違う仕事に挑戦し、第2の人生を謳歌する姿を紹介するものだ。このテレビ局は、田舎暮らしを楽園のように取り上げるのが好きなようで、他の番組でも似たようなことが取り上げられている。
私も時々見るが、正直なところ「眉唾ものだなあ」と思って見ている。そもそもこのような企画には、田舎はのんびりしていて、人々はお人好しで、何事にも寛容な優しい人たちのいるところ、という架空の前提が置かれているように思えてならない。
私は兵庫県の山の中で生まれ育った。水田はすべて棚田である。村の中に平らなところはほとんどない。結婚前に妻を連れて帰ったのだが、風呂は五右衛門風呂、便所は納屋の一角という光景に、泣きそうになったそうである。村全体が貧しかった。
家族が触れようとしない一軒家
私の生家から20メートルほどしか離れていない畑の一角に、戦時中、疎開していた人の小さな家がぽつんと一軒あった。私は終戦の3年後に生まれたが、物心ついた時には、その家にはもう誰も住んでいなかった。だがこの小さな家は、その後、建替えられて今も同じ場所にある。恐らく別荘代わりにして、時々利用しているのだろう。
子どもの頃からどこかで不思議に思っていたのだが、この家のことが家族で話題になることが、ほとんどなかった。“疎開してきた人が住んでいた”という以外の情報は皆無だった。死んだ母からも何も聞かなかった。今はひとまわり上の義姉が住んでいるが、まったく話題になったことがない。ボールを投げれば届くほどの距離なのに、あまりにも不自然である。
最近になって思うのは、一種の村八分状態に置かれていたのではないか、ということだ。
『国家の品格』の著者である藤原正彦氏が、あるエッセイの中で知り合いの若い百姓が詠んだ短歌を紹介している。それが次の歌だ。