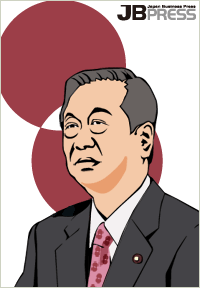2010年4月、文部科学省で静かな社会実験が始まった。その名は「熟議カケアイ:文科省政策創造エンジン」。専門のウェブサイトが立ち上がり、多くの教育関係者がこの新しい政策形成のやり方に期待を寄せる半面、かつて見たような「不毛な」党派対立に押し潰される懸念も大きい。果たして「熟議民主主義」は日本の政策現場に根付くのだろうか。その現状を分析し、課題を洗い出してみたい。
議論を通じて主張が変わる「熟議民主主義」
 「熟議カケアイ」実験を始めた文部科学省(撮影・中野哲也)
「熟議カケアイ」実験を始めた文部科学省(撮影・中野哲也)
「熟議民主主義」は deliberative democracy の訳。欧米の政治思想学者の間でこの20年ばかり盛んに議論されてきた概念である。日本でも篠原一・東大名誉教授が「討議デモクラシー」として紹介するなど(篠原一『市民の政治学:討議デモクラシーとは何か』(岩波新書、2004年)』)、過去数年の間に急速に浸透してきた。
選挙で投票後、多数決で選ばれた代表に政治の舵取りを委ねる――。「数こそ力なり」だから、少数者の意見は往々にして無視される。口惜しければ選挙で勝って多数派を形成するしかない。勢い、代表の数を取り合う争いが先鋭化し、争点がささくれ立ち、人々をムキにする。このような民主主義は「集計民主主義(aggregative democracy)」と呼ばれ、現代の民主政治の根幹を成してきた。
しかし、多数決は万能なのだろうか。
多数決は万能なのか(参考写真)〔AFPBB News〕
多数決で選ばれた代表にわれわれは本当に全てを委ねたのだろうか。多数を取るため、われわれは不毛な対決を続けなければならないのか。このような「集計民主主義」への疑問から、「熟議民主主義」はスタートする。
熟議民主主義では、自由で平等な市民が議論に参加し、互いに受け入れ可能な理由付けで結論を得る。現時点ではその結論と理由を皆が守るものの、将来また議論してもよいという政府の形である――。ペンシルベニア大のエイミー・ガトマン学長とハーバード大のデニス・トンプソン教授による共著『Why Deliberative Democracy?』(2004、Princeton University Press)は熟議民主主義をこのように定義している。
熟議民主主義では、関係者が直接一堂に会して議論を行い、対立する立場へのお互いの理解を深める。そして当初持っていたそれぞれの意見が変わっていき、熟成され、新たな解決策の創発が期待される。
田村哲樹・名大大学院准教授は著書『熟議の理由:民主主義の政治理論』(2008年、勁草書房)の中で、議論への参加者の理性と議論の過程での参加者の選好の変容を、熟議民主主義の中心概念と捉えている。
日本政府初の試み、マイクロソフトやヤフーも支援
熟議民主主義の実践例はデンマークやブラジルなどにあり、また日本でも三鷹市(東京都)や鹿屋市(鹿児島県)で行われているという。熟議をした集団としない集団では、議論の争点に対する合意形成が異なる。その効果を計測する「熟議世論調査」も欧米では結構実施されており、日本では曽根泰教・慶大大学院教授らのグループが神奈川県の藤沢市民を対象に2010年1月から調査を始めた。