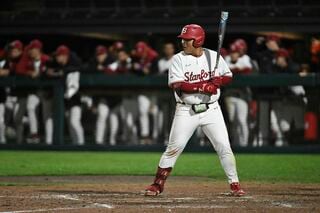世界一甘党の国、米国。
1人当たり、1年でおよそ60キロの砂糖をはじめとする様々な糖類を摂取している(米国農務省 2012年)。単純計算すると、1日に167グラムもの糖を取っていることになる。
食事と健康の関係が注目され、体重管理が全国的に広まった1970年代から現在まで、米国人は太り続けた。現在は、成人の3分の1以上が肥満だ(米疾病予防管理センター、2012年)。
塩分、脂肪分、肉、炭水化物、といくつも食品が次々とターゲットとなり、米国人の不健康の元凶だと敵視され、その後名誉挽回している。バターなどはいい例だ。あれほど体に悪いと食卓から追い出され、マーガリン使用が奨励され世界的に広まったというのに、実は上質のバターは体に良いと変わった。健康管理が一般的な関心事になってからというもの、数多くの「正しい説」や「体に悪いもの」が覆されてきた。
すっかり疑心暗鬼に陥っている一般市民の目の前で「今度こそ本物の悪者」として医学界に攻撃されているのが、砂糖や異性化糖などの糖類である。これが米国人の肥満と不健康の最大の原因だというのだ。
あらゆる加工食品に糖分が加えられている
ケーキや菓子類、ソーダ水を我慢すれば、“糖類断ち”ができると思っている人が多いはずだ。ところが、米国ではありとあらゆる食品に糖分が加えられている。自分で素材から料理しない限り、糖類を断つのは不可能な現状だ。
健康管理が注目され、「脂肪分の摂取を控えれば、心臓病が減る」と政府が奨励した70年代。食品会社はこぞって、製品の売り上げ増を見込んで「低脂肪」食品の開発を進めた。
国民も肉から脂部分を削げとり、牛乳は低脂肪に切り替え、「低脂肪」と宣伝されている食品を買った。
ところが、心臓病はもちろんのこと、肥満も糖尿病も激増し続けた。なぜか?
食品会社は、食べ物から脂肪を取るとうま味がなくなることを知っていた。そこで、脂肪を抜く代わりに、砂糖や異性化糖を大量に入れ、味が落ちないようにしたのだ。