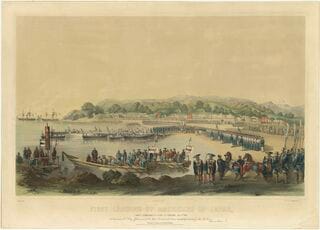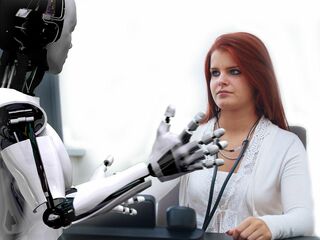東京の東銀座の駅近くに、“総菜屋のコロッケ”の草分けとして知られる店がある。1927(昭和2)年創業の「チョウシ屋」だ。
コロッケは、じゃがいもと挽き肉のオーソドックスな1種類のみ。ほかに、メンチカツやハムカツ、カツなどの揚げものがあり、いずれもコッペパンか食パンかを選んでサンドイッチにもしてくれる。
閉店間際に駆け込んで、最後に残っていたコロッケを2つ、ゲットする。手にすると、ほんのりと温かい。年代もののイラストがプリントされた紙袋に鼻を近づけてみると、ラードのこってりした匂いがかすかに漂ってくる。
形はもちろん定番の小判形。色は、キツネ色をやや通りこした茶色。さくりと衣にかぶりつけば、ほろりとじゃがいもが口のなかで崩れる。予想以上でも以下でもない、安心できる素朴な味わいだ。
この味を求め、開店当初は連日行列ができたという。値段は1個5銭。昭和の初め、そばが10銭、カレーライスが12銭だったことを考えると決して安くはないが、手の届かない値段ではない。今だって、揚げたてを待って買う時はワクワクするくらいだから、コロッケが高嶺の花だった当時の人にしてみれば、長い行列なんてどうってことなかっただろう。
 東京・銀座にあるチョウシ屋のコロッケ。現在の値段は1個140円。
東京・銀座にあるチョウシ屋のコロッケ。現在の値段は1個140円。
「肉屋のコロッケ」が広まるのも同じ頃だ。当時はまだ氷を使った冷蔵庫が一般的で、肉を長時間保存しておくと黒くなってしまう。こうした色の悪くなった肉や、加工の段階で出る細切れ肉を利用するには、コロッケはうってつけだった。また、揚げ油のラードが手に入りやすかったことも、肉屋とコロッケが結びついた一因だった。
こうして手軽に食べられるようになったコロッケは、現在に至るまでお惣菜の定番として変わらぬ人気を得ている。これまで紹介したカレーライスやとんかつなど、日本食と化した洋食は数多くあれど、コロッケほど「ごちそう感」が薄れ、庶民化した食べものはちょっと見当たらない。
だが、コロッケは最初から庶民の食べものだったわけではない。今回は、黎明期に絞って、コロッケの謎を追ってみよう。
「がんもどき」のようなじゃがいも料理だった
コロッケは、もともとフランスの「クロケット(croquette)」が転訛したものというのが定説である。