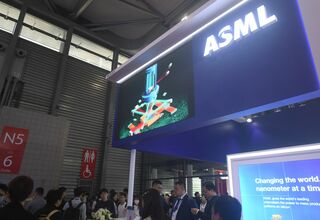秋から冬にかけては「そば」が旬の季節。秋の新そばが出回り、年末の「年越しそば」で最盛期を迎える。歳時記でもそばは冬の季語だ。
うどん、そうめん、中華麺、洋麺と、麺類は日本人の主食の1つとなっているが、頭に「日本」が付くのは「そば」のみ。日本人の麺食文化において、そばの存在を欠かすことはできない。
そんなそばと日本人の関わり合いの歴史はどのようなものだったのだろうか。歴史を探ってみると、今から400年ほど前、日本のそばの食べ方における“大きな変革”があったことが分かる。
前篇では、われわれが食しているそばが、どのように今のような形になっていったか、そばの食べ方、そばの供し方、そばへの見方などを追いながら、その歴史を辿っていくことにする。
その歴史の先端にあるのが現代だ。そば屋で食べる、そばを打つといった営みから発展して、そばは即席麺の世界にも広がっている。後篇では、食品メーカーによる「即席そば」の開発や、あまり日本人になじみのない珍しいそばの研究について見ていく。
日本のそばも、元をたどれば大陸伝来の食べ物となる。植物のソバの原産地は、DNA分析などから現在では中国雲南省からヒマラヤあたりにかけてという説が有力になっている。
だが、日本でソバの栽培が始まった時期はかなり古くまでさかのぼれる。日本史の中でも最も古い時代区分の縄文時代にたどり着くともいう。高知県内で9000年以上前の遺跡からソバの花粉が見つかり、当時からソバが栽培されていたと考えられているのだ。さいたま市岩槻区でも3000年前の遺跡からソバの種子が見つかっている。
「蕎麦」が初めて、歴史的文献に上ったのは、797年に完成した史書『続日本紀』においてである。奈良時代前期の女帝だった元正天皇(680~748)が出した詔の中に、次のような「蕎麦」の記述がある。
 ソバの実。ソバはタデ科の1年生植物。実の殻を除き、実の中に含まれている粉からそばを作る。種まきから収穫までは2~3カ月と短く、荒涼とした土地でもよく育つ。
ソバの実。ソバはタデ科の1年生植物。実の殻を除き、実の中に含まれている粉からそばを作る。種まきから収穫までは2~3カ月と短く、荒涼とした土地でもよく育つ。
「今年の夏は雨がなく、田からとれるものがみのらず、よろしく天下の国司をして、百姓(おおみたから)を勧課し、晩禾(ばんか)、蕎麦及び小麦を植えしめ、たくわえおき、もって救荒に備えしむべし」
日照り続きで稲の収穫が見込めない中、普通より遅く実る晩禾とよばれる稲や小麦とともに、栽培が推奨されたのが「蕎麦」だった。ソバは、日照りや冷涼な気候にも強く、また栽培する土地もさほど選ばないため、凶作の時も収穫が見込める救荒作物として位置づけられたのだ。