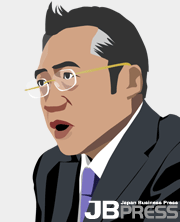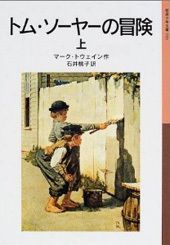改革を最も派手に表明したのが危機の震源地である米国だった。6月にオバマ大統領が発表した制度改革案は、業態ごとにバラバラだった監督機能を連邦準備制度理事会(FRB)に集約。銀行や証券会社、保険会社、金融取引を一元的に監視し、システムのほころびを早期把握するのが狙いだ。続いて、欧州連合(EU)は、欧州中央銀行(ECB)をベースに「欧州システミックリスク委員会(ESRC)」を発足させることで合意した。
金融庁幹部によれば、米欧で始まった制度改革は「流動性を供給する中央銀行が金融機関を目配りするため、軌道に乗れば、かなり詳細に個別のリスクを把握できる」。金融監督と金融政策の間の利益相反や中央銀行への権限集中を懸念する声は少なくはないが、「ミクロの金融監督だけでは危機を防げない」との恐怖感から、総論賛成の流れができている。
1997年秋、北海道拓殖銀行や山一証券が相次いで破綻し、日本は世界に10年以上先駆けて金融危機を経験した。その教訓から預金保険制度を整備し、監督・検査体制を強化し、日銀と金融庁が緻密に連携した金融システム監視網を築いてきた。金融庁幹部は、「マクロプルーデンスの観点から、日銀との関係をさらに深める必要がある」とするものの、「従来の欧米の監督体制に比べて先進的で、万全だ」と主張する。
確かに金融庁は銀行と証券会社、保険会社などの監督を網羅しており、かつての米国のような「規制のほころび」は少ない。
情報共有できない監督局と検査局
しかし足元で改革すべき点はないのだろうか。
多くの金融関係者が「改善余地がある」と指摘するのは金融検査のあり方だ。
米サブプライムローン問題がくすぶり始めた2007年以降、金融庁は検査局と監督局それぞれで民間の投資リスクの実態把握に力を注いできた。ところが、ある大手金融機関の幹部は「監督局に呼ばれて問われる内容と、検査官がやって来て聴取する内容がほとんど同じ。庁内で情報共有できていないのか」とあきれた表情を浮かべる。
背景には金融庁の検査部門と監督部門の指揮系統の分断がある。1996年の住専処理で不良債権を把握できなかったことや、98年に金融検査に絡む接待汚職事件が発覚したことで、大蔵省の金融行政は批判の矢面に立たされた。こうした流れの中で、金融監督庁が創設され、情報収集力の向上や、透明性確保の観点から、検査と監督は独立性を保ってきた。
しかし、若手官僚らからは「検査と監督の系統を完全に分ける必要性は小さくなっている」との声が出る。同庁幹部も「金融機関の複雑さが増し、実態の把握には検査と監督の有機的連携が不可欠になってきた」と問題意識を示す。
検査と考査の一本化を
さらに、金融検査は日銀考査との連携も課題のはずだ。
検査が法に基づく執行権であるのに対し、日銀考査は契約に基づく状況調査であり「業務目的も権限も異なる」(日銀)。しかし検査と考査は「ともに健全性維持が狙いであり、手法は似たりよったり」(邦銀幹部)。
その一方で、金融庁が新銀行東京への検査を検討していた2006年末に、日銀が考査入り方針を連絡し、同庁はタイミングを逸した――といったニアミスも少なくない。マクロプルーデンスを模索するならば、金融庁と日銀の連携強化は不可欠。いっそのこと検査と考査の共同実施、一本化を進めてもよいのではないか。
今回の危機では、日本の金融システムは米欧のような直接ダメージは受けていないだけに、「大規模な監督体制の再構築を推し進めるのは難しい」(自民党有力議員)。だが金融庁と日銀は、手持ちの材料でも、十分に実効性が高い「チューンアップ」ができるはずだ。