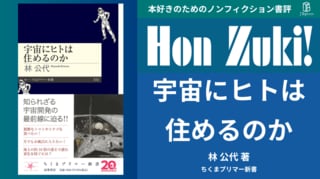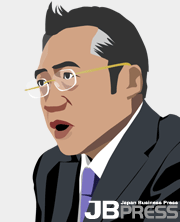末期的状況に陥っている麻生太郎政権。昨年9月の発足以来、一貫しているのは「100年に1度」の金融危機対応として続く財務相と金融相の兼任体制ぐらいかもしれない。
その体制下で7月に発表された財務省・金融庁人事では両省庁の接近が話題となった。金融庁の局長級である総括審議官が、財務省の関税局長に「復帰」。1998年に金融監督庁(現在の金融庁)が大蔵省(現財務省)から分離して以来、財金分離原則の下で守られてきた「ノーリターンルール」(金融庁局長を財務省に戻さない措置)が初めて破られたのだ。
財務省と金融庁は、不良債権処理をめぐる財政と金融の利害相反や金融検査をめぐる接待不祥事を踏まえ、異なる道を歩み続けてきたはずだ。それが財務・金融相兼任の解禁以来、両者は距離を縮めたように見え、霞が関OBからは「財金再統合」を期待する声も聞こえてくる。
マクロプルーデンスが世界の潮流に
しかし、大蔵省時代への郷愁が現実のものになることはないだろう。
ポスト金融危機をにらみ、国際的にはマクロプルーデンス(健全性維持)の視点を重視した金融規制改革が始まった。軸となるのは各国の中央銀行。金融庁で対外交渉に当たる幹部は「金融庁と日銀の連携が重要になる」と言い切る。
 財務省(手前)を見下ろす金融庁(奥右)。98年6月に金融監督庁が設置されるまでは同じ役所だった
財務省(手前)を見下ろす金融庁(奥右)。98年6月に金融監督庁が設置されるまでは同じ役所だった
もちろん、金融庁の幹部職員は大蔵キャリアが大半を占めるだけに「財務・金融一体となった人事の帳尻合わせ」は今後も続くことになる。それでも「業務で接点が増すのは財務省より日銀だ」と言う。
金融監督庁として分離後10年超、金融庁は財務省との距離を意識して動いてきた。しかし、米欧の金融監督制度が中央銀行を巻き込んで転換する中で、金融庁は今後の10年で日銀との距離を測りつつ「大蔵省解体」以来の改修を迫られる可能性がある。
木を見て森を見ていなかった金融監督
これまでは、木を見て森を見ていなかった?〔AFPBB News〕
これまで、日米欧などの金融監督は「個別の金融機関の健全性を確保し、利用者を保護する」というミクロの視点に力点を置いてきた。しかし、今回の危機を経て、「木を見て森を見ず」だったことが露わになった。
この20年、米欧の巨大金融機関は国境を越え、活動範囲を拡大。その上、証券化やデリバティブ、さらに簿外処理による「影の銀行システム」でリスクを飛ばしてきた。結果が信用バブルの生成と崩壊だ。国際金融筋によると「個々の銀行が見かけ上の健全性を保ったまま、金融システム全体のバランスが崩れていった」。
予兆を見逃した反省から、米欧の金融当局や中央銀行は今年、相次ぎマクロプルーデンス重視の枠組みへと舵を切り始めた。「木=個々の金融機関」の健全性を監視しながら、金融政策・分析も活用して「森=金融システム全体」の安定性を高め、次の金融危機を警告する「木も、森も見る」政策だ。