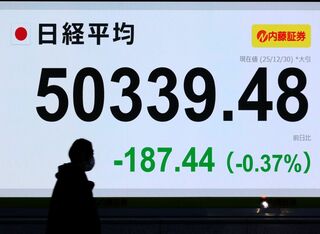ダボス会議に出席、スピーチするトランプ大統領(1月22日、写真:ロイター/アフロ)
ダボス会議に出席、スピーチするトランプ大統領(1月22日、写真:ロイター/アフロ)
(英フィナンシャル・タイムズ紙 2026年1月22日付)
70年前、ともに衰退していた英国とフランスはスエズ運河を武力で奪おうと試みた。奇妙なことに、どちらの国の指導者も明らかな好戦的な愛国主義者ではなかった。
英国の首相はアンソニー・イーデン。アラビア語とペルシア語に通じた、戦後のダウニング街10番地の主としては最も教養ある人物だ。
これはただ、分別のある人でも自分の地位についての不安が強まると無分別な行為に走ってしまうというだけの話だった。
フランスはアルジェリアで勝つ見込みのない戦争をし、英国はユーロ連邦主義者のプロジェクトに未来はないと考えて参加を見送った。どちらの判断ミスも、いまだに両国に影響を及ぼしている。
米国の衰退
もちろん、米国の衰退は当時の英国やフランスほど急激ではない。2番手との差が縮小したとはいえ、いまだ地球上で最強の国家だ。
だが、別の意味では、米国の衰退の方が深刻だ。
当時の英国はずっと、民主的で英語を話す、大部分が白人の超大国にバトンを渡すのだと言って自分を慰めることができた。対照的に米国は、そうした特徴を全く共有していない中国に追い上げられている。
そのため、その地位の落ち方は客観的に見れば英国よりもはるかに緩やかなのに、主観的には英国よりも苦しいのかもしれない。
どの国に対して衰退しているかは大きな問題なのだ。
この方程式を、「格」へのこだわりがドナルド・トランプ並みに強い――格の違いをほとんど地層のように意識している――誰かに当てはめてみよう。
すると、グリーンランドに対するひどい扱い、カリブ海での砲艦外交、そして失われた威厳を取り戻そうとするスエズ戦争式の試み(オリジナルよりは若干成功しているかもしれない)といった解が得られる。
だが、たとえ普通の大統領が率いていたとしても、米国は今頃には、ひどい振る舞い方をしているのかもしれない。
地位の低下に怯える国は虚勢を張る。衰退をあっさり認める超大国はまれだ。