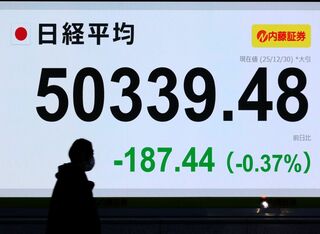トゥキディデスの言葉は正しいのか?
古代ギリシャの歴史家トゥキディデスは「強者はできることをやり、弱者は耐えねばならないことに苦しむ」と語った。
この言葉が最近、頻繁に引き合いに出されている。そういう時には、これが国際関係に関する苦々しい、しかし普遍的な真実であることを表現しているかのごとく深く頷いてみせるものだとされている。
しかし、本当にそうなのか。このフレーズは、国家が強くなるにつれて攻撃的になることを示唆している。
考えてみよう。米国は、トランプが生まれた1946年前後が最も強かった。世界の製品の半分を製造し、核兵器も独占していた。それほどの力がありながら、米国は「できること」を弱者に対してやらなかった。
それどころか、賢明な利己心の模範であるマーシャル・プランと北大西洋条約機構(NATO)を立ち上げた。日本とドイツを平和主義の民主主義国として復興させた。
つまり、米国の行動が好戦的になったのは相対的な衰退が進んでいる時だったわけだ。
そうした行動の一部は、リーダーが誰であったかで説明できる。
その点、ハリー・トルーマンはトランプより「優れていた」が、それはいくらかそうだったに過ぎない。それ以外のことは構造的な要因による。
国家というものは、絶頂期にある時の方が寛大になりやすい。偏執的で攻撃的になるのはそうした地位から滑り落ちる時だ。
だとすれば、我々は米国が唯一の超大国ではなく、いくつかある超大国の一つという役割に慣れるまで、米国が荒々しい行動を取るのを覚悟するべきなのだろう。
英国もフランスも、もっと凋落しなければならなかったとはいえ、結局そこに落ち着いた。
ディラン・トマスが衰退について書いた有名な詩の一節を引用する人はいない。
トマスは「消えていく光に怒る」よう読者をせっついた後、あきらめる方が理にかなっていると引き下がる。「最期を迎える賢者は、暗やみが正しいことを知っている」と言う。
トランプは怒りを好むが、彼の立場に立たされたら、ほかの指導者たちも同じだろう。
(文中敬称略)