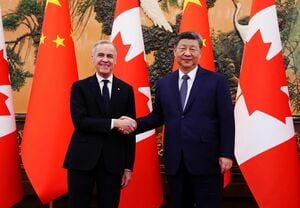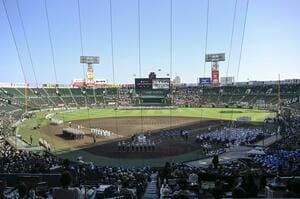広告代理店に頼らず成功した東京デフリンピック、運営本部COOが明かす低コスト運営の裏側
広告枠を売らず、課題解決をアピール、160社を巻き込んだ準備運営本部のスポンサー獲得術
田中 圭太郎
ジャーナリスト、ライター
2025.12.30(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら