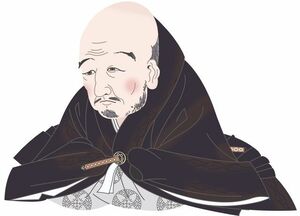目指したのはギリシア芸術最盛期の彫刻の美
ヴィスコンティ監督はトーマス・マンの小説によほど傾倒していたのか、ほぼ原作通りに映画を創っている。殊にタッジオの描写に関しては、衣裳や髪の形から表情、仕種にいたるまでマンの記述を忠実に映像化している。おそらく、脚本に取りかかる前に、ヴィスコンティの頭の中には既に明確なコンテが出来上がっていたのだろう。
そして、タッジオ役のビョルン・アンドレセンに求められたものは、「演技」ではなく「ポーズ」だったに違いない。少年は、監督の思い描く構図の中で指示通りの美しい「ポーズ」を取ることに専念し、「演技」のほうは明らかに、それを受けたダーク・ボガードにすべて委ねられている。マンの小説では、アシェンバッハが最初にタッジオを見た印象を「ギリシア芸術最盛期の彫刻を思わせる」と表現しているが、ヴィスコンティが最も心を砕いたのは、それと同じ印象をいかにして観客に抱かせるかという点であったように思われる。
ドイツ軍占領下のフランスで創られたマルセル・カルネ監督の『天井桟敷の人々』(1945年)という作品がある。男たちを虜にする美人女優をめぐる波乱万丈の恋愛ドラマで、フランス映画史上ベスト・ワンにも選ばれた名作であるが、ぼくの心にはまったく響かなかった。理由は簡単である。絶世の美女に扮したアルレッティという女優さんが全然きれいでなく、ぼくにはただのおばさんにしか見えなかったのだ。
その点、ヴィスコンティは繊細である。マルセル・カルネは美しさを演技で表現しようとしたが、ヴィスコンティの審美眼はそれでは満足できなかったのだ。
『ベニスに死す』では、タッジオの美しさを強調するために、2つの制約を設けている。第1の制約は、アシェンバッハとタッジオに会話をさせないということである。アシェンバッハは常にタッジオの側にいて賛嘆の眼差を注ぎながら、一度も言葉を交さない。それは、ふたりの間に人間的な関係が生じれば、それだけ造形的な美しさが損なわれるからだ。15歳の少年が言葉を発すれば、そこに年齢相応の感情や性格が表われ、神々しさは失われるだろう。それゆえに、アシェンバッハは焦がれ死にするほどタッジオを崇拝しながら、ただ眺めているほかないのである。
2つ目の制約は、アシェンバッハの一人称でドラマを創るということである。タッジオの登場するシーンはすべてアシェンバッハの視点でつくられていて、映像には彼の気持が反映されている。そのため、観客は意識せぬままに、タッジオを崇拝するアシェンバッハと同じ目線で少年を見せられているのである。この効果は絶大で、劇中のタッジオのみならず、彼に扮したビョルン・アンドレセンまでが神格化されてしまった結果、今ではスクリーンに写っている少年をタッジオとしてではなくビョルンその人だと錯覚して見てしまうほどになっている。
ヴィスコンティの映画は緻密で計算され尽している。何を美しいと思うかは人それぞれの主観の問題で好き嫌いの分かれるところであるが、モネやルノワールの絵画は観る者の好悪の感情を超えた価値を持つ。ヴィスコンティの作品も同様である。
映画を芸術とするならば、ヴィスコンティほどそれを体現した監督はいない。ビョルン・アンドレセンが半世紀を経てなお最も美しい少年であり続けたように、『ベニスに死す』も、たとえ百年が経過しようとも、他のいかなる映画の追随も許さぬ孤高の作品であり続けるだろう。
(編集協力:春燈社 小西眞由美)