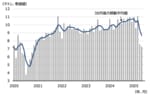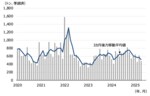レアアースの輸出制限でEV関税の撤廃を目論む中国に揺さぶられる欧州、簡単ではなかったEUの対中デリスキング
【土田陽介のユーラシアモニター】中国の強みを再認識させたトランプ関税と中国が欧州に仕掛けたディール
2025.7.5(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
銅に50%、医薬品に200%、強気に戻ったトランプ政権のアキレス腱、関税交渉の難航で再び忍び寄るドルショックの影

あわせてお読みください

トランプ関税で「米国にまともな工場」は無理ゲー、「価格転嫁せず」も筋違い……様子見一辺倒の日本企業
【JBpressナナメから聞く】オウルズコンサルティンググループCEO・羽生田慶介氏①
羽生田 慶介 | 細田 孝宏

トランプ関税で進む「チャイナプラスワン」、実は有望な拠点は日本?ASEANに上から目線の「老害企業」は時代遅れ
【JBpressナナメから聞く】オウルズコンサルティンググループCEO・羽生田慶介氏②
羽生田 慶介 | 細田 孝宏

財政拡張路線に舵を切ったドイツだが、労働力不足というボトルネックの下、本当に景気回復につながるのか?
【土田陽介のユーラシアモニター】前年比6%増となる拡張予算を組むメルツ政権、サボリ癖がついたドイツ人の動向が鍵
土田 陽介

EUが推し進めるエネルギーの「脱ロシア化」は本当に可能か?ロシア産天然ガスの完全禁輸法案が占うEUの“結束力”
【土田陽介のユーラシアモニター】ガス禁輸でハンガリー外しを目論む欧州委員会だが、ロシア産ガスの輸入は続きそう
土田 陽介

ドイツ人は働き者でギリシャ人は怠け者というイメージは真逆だった!労働統計が明らかにした欧州のウサギとカメ
【土田陽介のユーラシアモニター】分配強化でサボリ癖がついたドイツの労働者、今やギリシャ人より働かない国民に
土田 陽介
本日の新着

家賃と携帯は滞納中、2カ月に1回の年金は外食で溶ける、収入のない年末年始を生き抜く高齢派遣労働者のゆく年くる年
【令和版おじさんの副業NEO】困窮する高齢者の年の瀬
若月 澪子

【2026年初詣】個人投資家「午(うま)尻下がり」相場に対抗する、午年に訪れたい干支ゆかりの神社仏閣
ビジネスパーソンから信頼厚い神田明神、愛らしい神馬のポニー3頭が待つ五方山熊野神社…都内近郊で馬にゆかりの初詣先
森田 聡子

窮地で「反米」に活路求めだした李在明の危険な賭け、国連総会でトランプをあてこすり、トランプ主催の晩餐会も欠席
[2025年を振り返る]【JBpressセレクション】
李 正宣

中国軍が「占領」か「失敗」か…台湾有事で起こり得る4つの事態、元幹部自衛官が考察してみると?
台湾有事は既に始まっている 「自衛隊は中国軍にかなわない」という言説を日本に広めたい中国の深謀
数多 久遠
欧州 バックナンバー

EUのEVシフトに公然と反旗を翻したドイツ、凋落するフォルクスワーゲンやメルセデスベンツを前に現実路線に回帰
土田 陽介

もし親に「殺してくれ」と懇願されたら?8割が安楽死容認の国で起きた「愛ある殺人」の波紋
松沢 みゆき

「ドイツに学べ」はもはや過去の話、フリーフォールと化したドイツ経済、メルケル時代の負の遺産に直面して悶絶
唐鎌 大輔

「仕事を辞めて“専業彼女”になりたい!」男女平等先進国のスウェーデンでZ世代の若者に広がる新しい価値観
松沢 みゆき

「トランプ・コロラリー」の衝撃、NSSが明文化した「脱欧」路線でNATO加盟国の“徴兵復活”は加速するのか
深川 孝行

「政治家4人に1人が日常的に脅迫や嫌がらせの被害」スウェーデンにも忍び寄る民主主義の脅威
松沢 みゆき