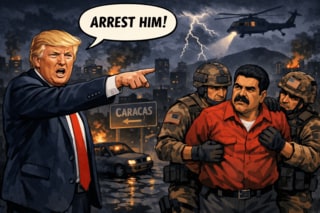当時、美智子さまについて「育ちがいい」と母がいった。「育ちがいいってどういうこと?」と聞き返したが、どうやらうちの近所のお転婆とは違う、ということらしい。
週刊誌のグラビアで、美智子さんが歩いている姿を男の子が初心者向けカメラ「フジペット」で撮影しているシーンが掲載されたのを見た記憶がある。子どもまでがお二人の婚約に熱狂したのだ。
東京からはるか離れた、筆者が住む九州の地方都市にもミッチーブームはやってきた。近所の駄菓子屋では美智子さんの着せ替え紙人形が売られていた。やはり近所の酒飲みオヤジは、赤ら顔で「皇太子は粉屋の娘と結婚するらしい」と訳知り顔で吹聴していた。
皇室入り後の心労
ご成婚は昭和34年4月10日。大卒サラリーマンの初任給がおよそ1万5000円の時代である。その年の出来事の中で、皇太子・明仁親王と美智子さんのご成婚以外で筆者の印象に残っているのは、南極観測隊員が置き去りにした樺太犬のタロとジロが生きていたことだった。実に驚きだった。他には伊勢湾台風、安保反対闘争。普及し始めたテレビでは『月光仮面』や『ポパイ』など、子どもたちの心を躍らせる番組が目白押しだったが、ミッチーブームはテレビの普及に大いに貢献したらしい。
当時は第一次ベビーブームの子どもたちが小学校高学年くらいの年代だ。私より少々上の世代だが、われわれも含め、近所には子どもが湧くようにいた。昭和30年代の田舎町だけに、子どもたちもたくましく、厚かましくもあった。夏休みになれば、朝のラジオ体操の後、町内で飛び回るハエをハエたたきで潰し、マッチ箱に詰めた。ハエでいっぱいになったマッチ箱は保健所が30円で買い取ってくれた。衛生対策の一環だったのだろうか。
近所で葬式があると、葬式まんじゅうをもらうため集まっていた。バキュームカーが来ると鼻をつまんで興奮した。床屋に行くと前髪を横一列に切られ、首筋あたりにはてんか粉(ベビーパウダー)を叩かれた。甘い匂いがくすぐったかった。そこら中に野良犬がうろついており、狂犬病を防ぐため保健所の野犬捕獲員が、針金で作った輪を先端につけた棒を持って野犬狩りをしていた。
学校では年がら年中、やれチフスだ、やれジフテリアだ、やれBCGだとさまざまな予防注射を打たれた。針の使い回しもあったという。今から思うと、貧乏で不衛生な時代だったが、やはり懐かしくもある。今よりも人々には漠然とした夢があり、日常の中には笑いもあった。
そんな雑然とした騒がしい世の中ではあったが、皇太子のお妃が一般人で、しかも学習院ではなくカトリックの聖心女子卒の美智子さんであったことで、国民は皇室、そして美智子さんに親近感を覚えるようになった。