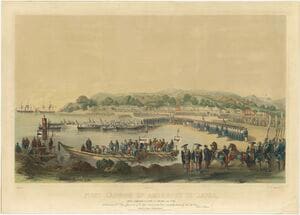好成績でも人気薄の理由とは?
こうした実績にもかかわらず、オペラオーの人気度は現役当時だけでなく、引退後も思ったほど伸びることはありませんでした。以前にもご紹介しましたが、月刊誌『優駿』読者が選ぶ「未来に語り継ぎたい名馬BEST100」(2024年9月号)でオペラオーは第13位となっています。
この馬の輝かしい実績からすると低い評価と言えますが、実はこの評価にこそ他馬とは一味違うこの馬の魅力が隠れている、と私は思うのです。
こうした人気投票では、大きなレースでどれほどの着差をつけて勝利したのか、その勝ちっぷりを高く評価したり、あるいは故障や連敗によって一度奈落に落ちた人気馬が復活するという物語に感動したりするなど、その馬が見せてくれた圧倒的な強さや負けっぷりも含めた個性やドラマ性にファンは惹かれるため、オペラオーのように接戦の多い勝ち方は印象度アップに貢献してはくれなかったのでしょう。
オペラオーの最大の武器はその精神力にありました。G1レース7勝の際、2着馬との差は、レース順に①首、②3/4馬身、③首、④2馬身半、⑤首、⑥鼻、⑦半馬身というように1馬身以上の差をつけて勝利したレースは1度しかなく、勝利した7レースの着差の合計は4馬身ほどにしかなりません。
今から40年前の1985年に日本初の7冠馬となったシンボリルドルフの場合、7冠レースで2着馬につけた着差トータルは約14馬身というものでした。
シンボリルドルフの勝ち方と比較したときに両馬の印象度に違いが出てくるのは致し方ありませんが、見方を変えると、オペラオーの勝負強さがあぶり出されてくるとも言えるのです。追いつかれても絶対抜かせないという比類なき勝負強さは隠れた魅力でもあったのです。
オペラオーは皐月賞に勝利した馬ではありましたが、デビューの頃から騒がれていた馬ではありませんでした。ミスターシービー(1983年)、シンボリルドルフ(1984年)、ナリタブライアン(1994年)、ディープインパクト(2005年)、オルフェーヴル(2011年)、コントレイル(2020年)という歴代6頭の3冠馬は皆、デビューの頃から注目され、新馬戦やクラシックレースの前哨戦で勝利し、人気と実力を兼ね備えたエリートたちでした。
反して、オペラオーの初勝利は3戦目、遅い初勝利だっただけに皐月賞には追加登録料の200万円を支払って出走、皐月賞を制覇したことによって、この登録料は無駄にはならず、その後の名馬誕生につながりました。このようにG1初制覇までには前述の名馬たちとは一味違う道のりがありました。