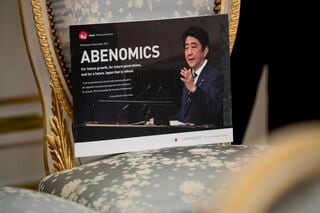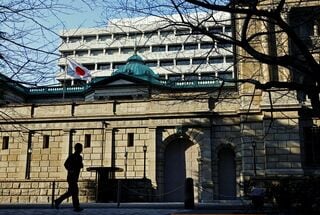日経平均は昨年7月11日に最高値をつけた(写真:つのだよしお/アフロ)
日経平均は昨年7月11日に最高値をつけた(写真:つのだよしお/アフロ)
トランプ関税で足もとの株式市場は揺らいでいるが、過去3年を振り返れば、日経平均株価は50%近く上昇した。不動産をはじめとした資産価格も高騰しており、一見、活況を呈しているように見える。だが、その間に起きたことはインフレによって名目ベースの資産価格が切り上がっただけ。起きている現象は、インフレと通貨安に苦しむ新興国と変わらない。(唐鎌 大輔:みずほ銀行チーフマーケット・エコノミスト)
株高に透ける日本の危うさ
ロシア・ウクライナ戦争開戦から丸3年という節目を超えた3月4日、「日米の金利差縮小でも超円安は解消しなかった……ロシア・ウクライナ戦争の開戦から3年で変貌した日本経済の現在地」と題した記事を出した。
その中で、過去3年間の日本経済については「日銀による利上げの遅れや資源価格の高騰を背景に、金利・需給両面から円売りが強まり、多大なインフレ圧力が輸入され、実質ベースでの成長が滞った」と総括した。
もっとも、円安とインフレが顕著に進み、景気が停滞する中でも国内の株価は急伸した。3月に入ってから大きな調整に見舞われているものの、それでも3年間という期間で見ればかなりまとまった幅の上昇を経験したのも事実だ。
この状況をどう解釈すべきだろうか。
筆者は、こうした株高は日本経済の置かれた状況が先進国というよりも、高インフレを抱える新興国に近づいている兆候として懸念する立場だ。この点は株価や為替、インフレの動きを国際比較することで見えてくる。今回はこの点を掘り下げたい。
既報の通り、パンデミック以降の日本経済では、不動産価格や株価が顕著に押し上げられている。
例えば、日経平均株価は2022年2月24日から2025年2月24日までの3年間で日経平均株価は+50%近く上昇した(2万5970円82銭→3万8776円94銭)。教科書通り、通貨安に焚きつけられたインフレによって、名目ベースの資産価格が切り上がっていると考えるのが自然だろう。
次ページの図表①を見れば分かる通り、「自国通貨安で高インフレに陥る国の株価指数は押し上げられる」という状況は、トルコやアルゼンチンのような高インフレ・通貨安で悩む新興国に象徴的な現象である。