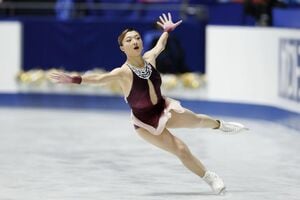これまでも暑さ対策はしてきたが、まだ足りない
夏の甲子園大会はこれまで、どんな暑さ対策が講じられてきたのでしょうか。
まずは試合間隔の調整です。夏の高校野球は過去、連日試合が行われていましたが、選手の疲労回復を考慮し、「ともに1日で行われる準々決勝と準決勝の間に試合のない休養日を1日設ける」(2013年)、「準決勝と決勝の間にも休養日を設ける」(2019年)、「3回戦の最終日と準々決勝の間にも休養日を設定」(2021年)といった策を講じました。また、午前9時半の試合開始を午前8時に繰り上げるなど、比較的涼しい時間帯に試合を行うように調整を進めました。
選手の熱中症対策として、試合中に「クーリングタイム」を設けるようになったのは、2023年からです。5回終了後、10分間の休息を取り、体調を整える時間としました。この年には、ベンチ入り選手を18人から20人に増やす措置も取りました。かつてのようにエースが1人で投げきるスタイルが減り、複数の投手で戦うことが当たり前となったことなどから、交代要員を少しでも多くし、選手の負担軽減を目指したのです。
この間、暑さ対策として白色のスパイクを認めたり、ベンチ裏で理学療法士が待機したりするなどの対策も導入するなど、細かな暑さ対策も行われています。
夏の大会だけの対策ではありませんが、選手を酷使してしまうことへの反省から投手の投球数制限や延長戦の改革も行われてきました。
2006年には「ハンカチ王子」として人気を集めた早稲田実業の斎藤佑樹投手(元日本ハム)は1週間で689球、「カナノウ旋風」を巻き起こした2018年の金足農業高校(秋田県)の吉田輝星投手(オリックス)も1週間で500球以上を投げました。こうした過度の投球は高校生の肉体に過度の負担をかけ、選手生命を左右する恐れもあることから、2020年の春の甲子園大会から「1週間に500球」という上限が設けられたのです。
また、かつては18回まで戦うことになっていた延長戦は段階的に短くなり、2018年からは春の大会でタイブレーク制を導入。2023年からは春夏ともに甲子園大会のすべての試合で、10回以降はタイブレークで行うことになりました。
この制度では、ノーアウト1塁・2塁の状態でプレーを開始するため、必然的に得点の可能性が高くなります。長い延長戦を避けることで、選手を疲労させないことを狙っています。
それでも暑さ対策は十分ではありません。もっと別の対策が必要ではないか。そうした議論の末に2024年から登場するのが、甲子園大会の「2部制」です。